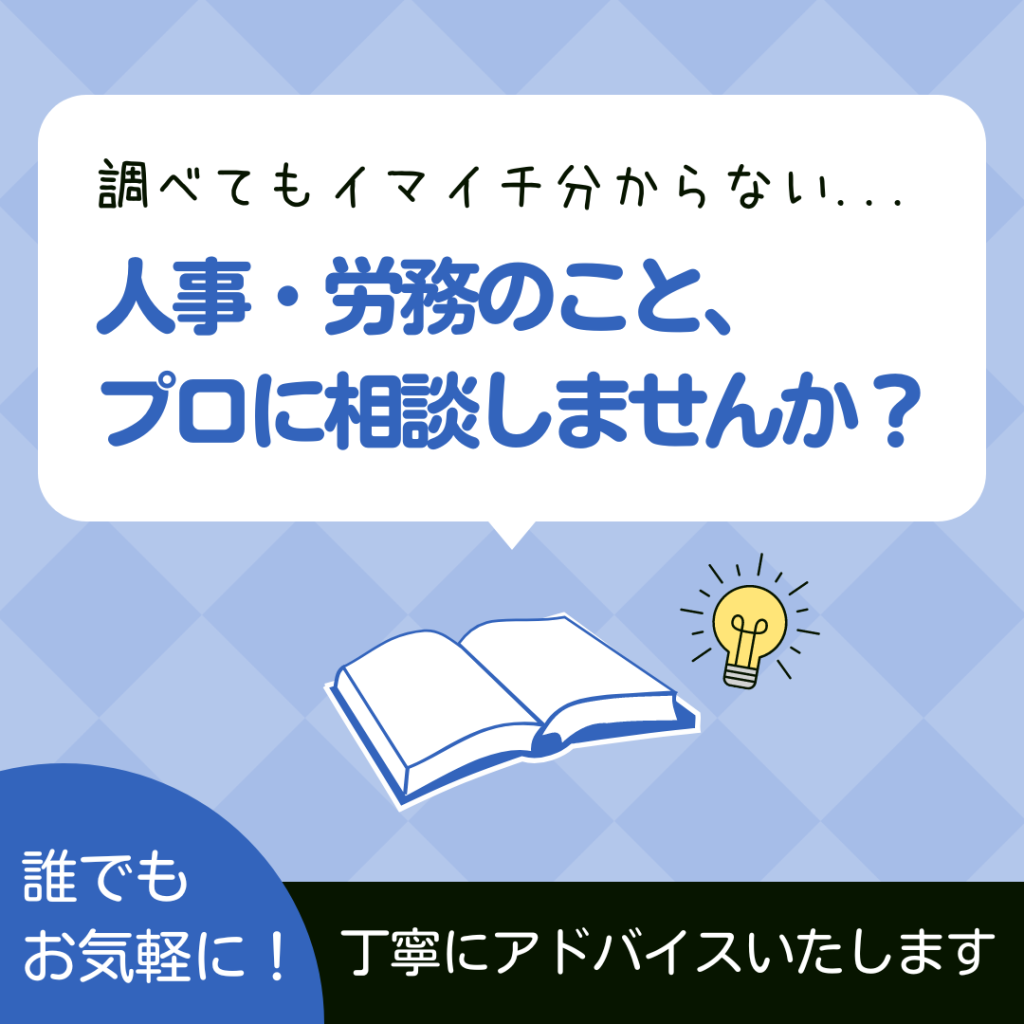11月は「過労死等防止啓発月間」です~長時間労働解消と健康管理の重要ポイント~
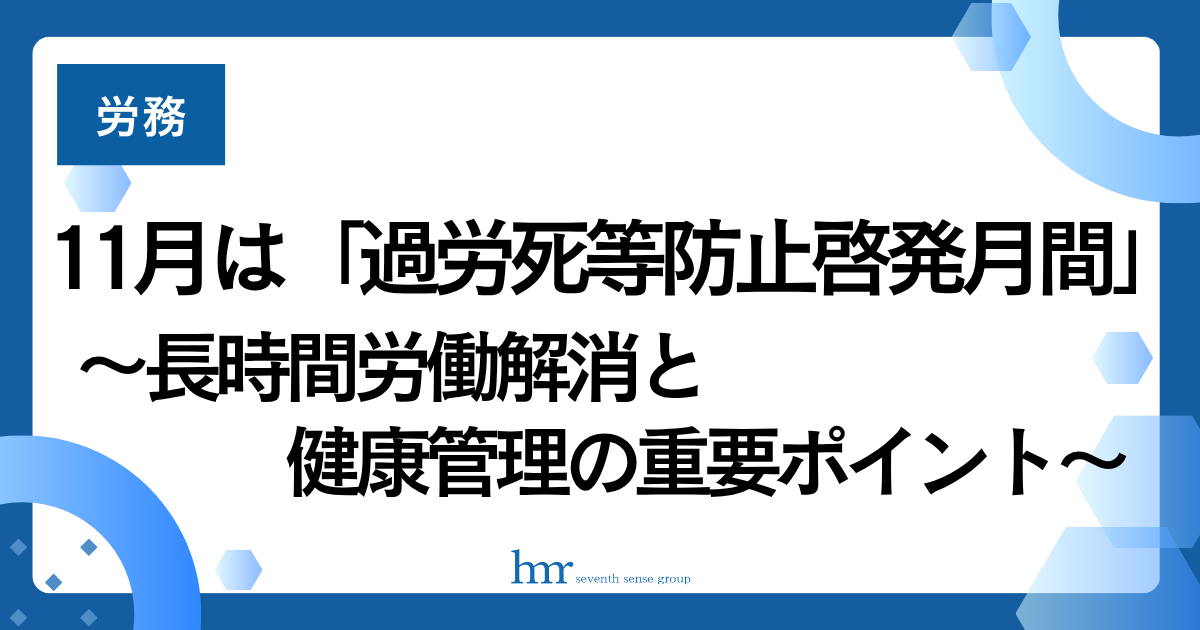
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
さて、今年も11月は「過労死等防止啓発月間」です。
厚生労働省は、「しごとより、いのち。」をスローガンに、過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けられる社会を目指しています。
この月間に際し、特に重要な長時間労働の解消と健康管理についてお伝えします。
1.過労死等のリスクと労災認定基準
過労死等は、過重な業務による脳・心臓疾患や精神障害が原因の死亡や疾患です。
特に、長期間の過重労働は、脳・心臓疾患の重要な発症要因とされます。
脳・心臓疾患に係る労災認定基準では、週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるとされています。
特に、発症前1か月に概ね100時間、または2~6か月にわたり1か月あたり概ね80時間を超える場合は、健康障害リスクが「高」と評価されます。
2.過労死等防止に向けた国の目標と対策
過労死等防止のため、長時間労働の削減やワーク・ライフ・バランスの推進が急務です。
国は、以下の目標を設定し、企業に取組を促しています。
●長時間労働の削減
・週60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(2028年まで)。
●休暇取得の促進
・年次有給休暇の取得率を70%以上とする(2028年まで)。
●健康管理・メンタルヘルス対策
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上とする。(2027年まで)
・小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上とする。
(2027年まで)
事業主は、労基法及び安衛法により、労働時間を適切に管理し、その状況を適正に把握する責務があります。
労働時間を正確に把握し、過重労働による健康障害を防止するための措置を徹底しましょう。
また、裁量労働制対象者や管理監督者についても、労働安全衛生法に基づき、医師による面接指導等の必要な措置を講じなければなりません。
3.勤務間インターバル制度の導入
終業から始業までに一定時間以上の休息を設ける制度で、2019年4月から事業主の努力義務です。
従業員の健康維持・向上や生産性向上につながるため、国も導入を促しています(2028年までに30人以上の企業で の導入率15%以上目標)。
労働者の健康を守り、活力を高める職場環境づくりは、企業の持続的な成長に不可欠です。
この機会に、労務管理体制を見直し、より良い働き方を推進していきましょう。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。