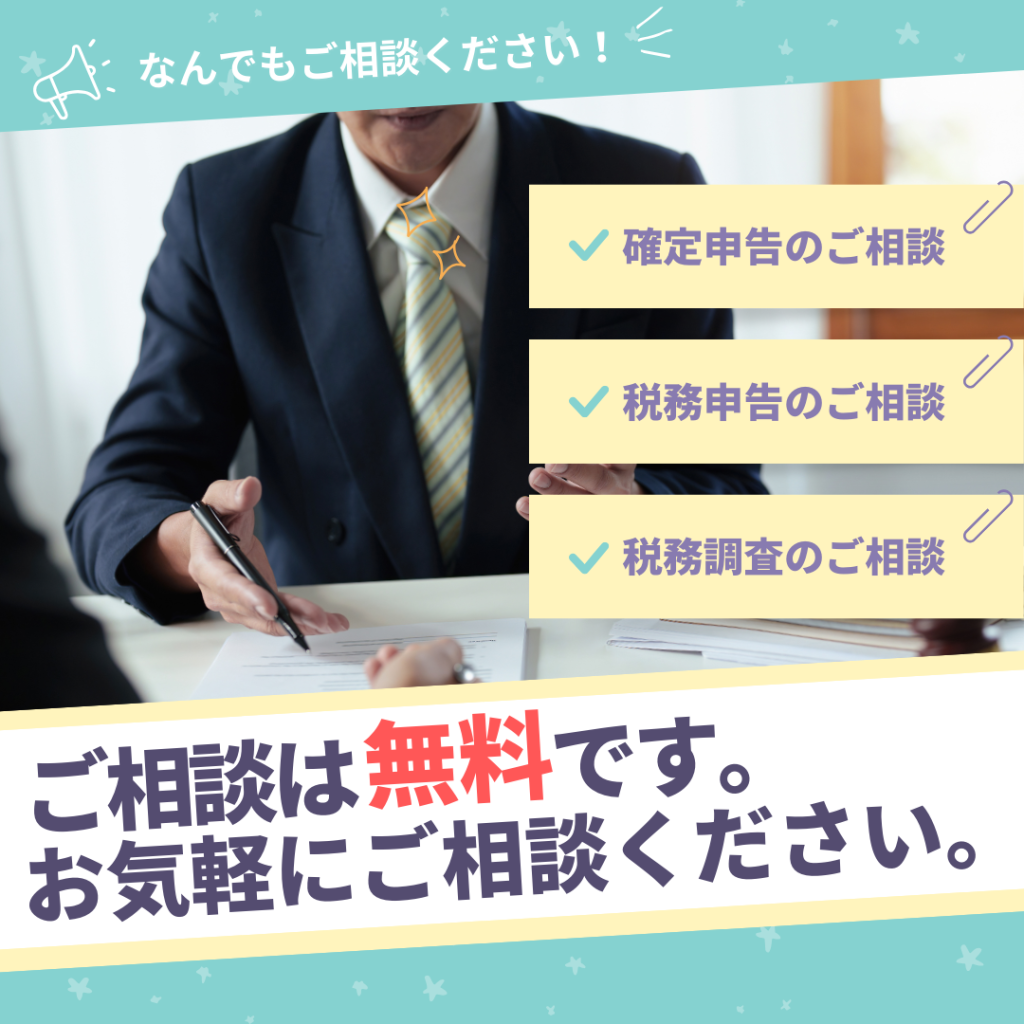骨格材の太さを調べる調査官など税務署には絶対にいない
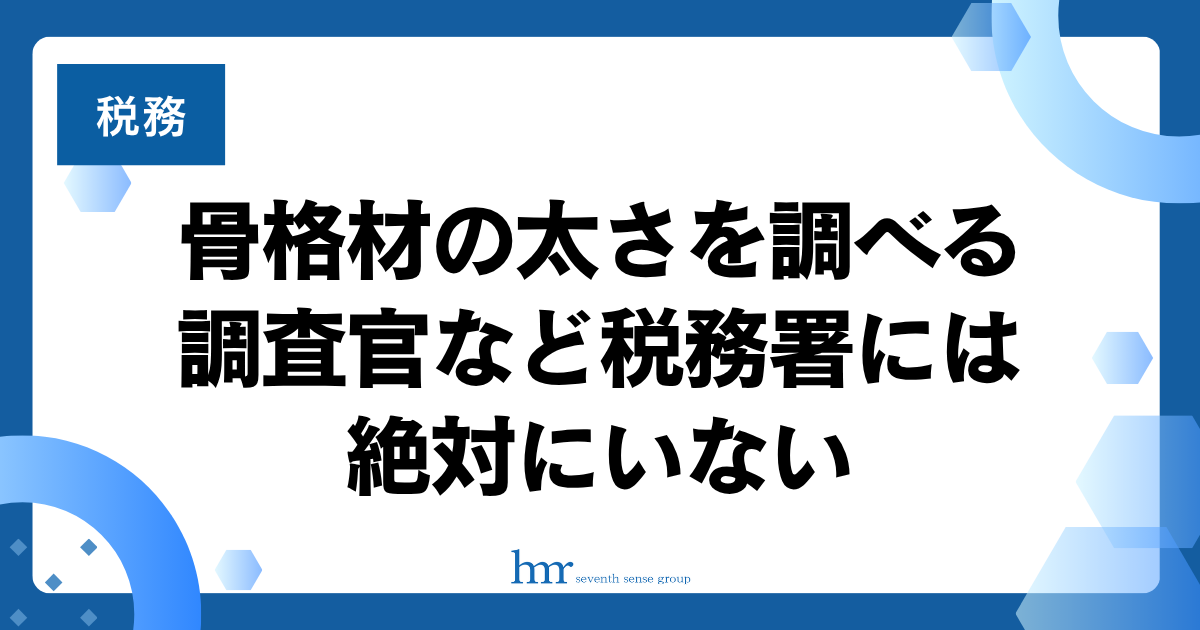
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第五百十八回目。
テーマは、「骨格材の太さを調べる調査官など税務署には絶対にいない」です。
ある税務雑誌で特集されていた審査請求事例ですが、建物の法定耐用年数について争われた事例があります。
この事例においては、ストレートに耐用年数を争ったものではなく、そもそもは相続により取得した建物の減価償却の処理が問題になっています。
この事例における納税者は、相続した建物について、その減価償却の方法を被相続人と同様の、定率法という方法で計算していました。
税理士の中でもミスが多いと言われる事例ですが、相続した減価償却資産については、
① 帳簿価額として引き継ぐ価格や耐用年数は被相続人と同じものを使う
② 減価償却方法については、被相続人と同じ方法を使わず、相続により取得したタイミングで適用できる方法で計算する
こととされ、被相続人の処理を引き継ぐ場合と引き継がない場合とそうでない場合とがあり、混乱することがあります。
建物については、平成10年4月前は、定率法という方法で計算することが認められていました。
しかし、この方法だと、多額の減価償却費が早期に計上できるため、税収が減り、現状は建物の減価償却は定額法という方法に一本化されています。
このため、この納税者の方は処理を誤っているとして、税務署から課税処分を受けることになりました。
引き継ぐ価額と耐用年数は被相続人、減価償却方法は相続時点と、混乱させる法律があることは確かに問題です。
しかし、納税者の処理には法律上は明白な誤りがありますから、税務署の主張は間違っていません。
しかし、この納税者は、償却方法ではなく、それとは別の建物の骨格材の肉厚を問題として、税務署の処理を問題にしています。
建物の法定耐用年数は、店舗用など、その用途によってだけではなく、骨格材の肉厚によっても変わることとされています。
このため、正確に耐用年数を当てはめるのであれば、骨格材の肉厚も調べなければなりません。
しかし、骨格材の肉厚を調べず、納税者が申告した法定耐用年数を基礎として税務署は課税処分をした模様です。
一方で、納税者は税務署と争う前に、再度きちんと肉厚を調べたら、そもそもの確定申告で使っていた耐用年数が違っていたことが判明しました。
その上で、正しく骨格材の肉厚を当てはめて計算すると、税額が下がることが分かったのでその点を審判所に主張したようです。
結果、審判所はその主張を認め、税務署の課税処分を取り消したようです。
一見して、税務署に問題がないと思われるケースであっても、あきらめずに何か勝てる要素がないか探してみることも、税務実務では非常に重要です。
なお、元国税調査官の立場から申し上げれば、手間がかかりすぎるため、課税処分前に建物の骨格材の肉厚などを税務署が調べることはまずありません。
それどころか、そもそも確定申告で適用した、耐用年数が正しいかどうか、チェックすることも基本ありません。
このため、本件は誤った課税処分がなされるべき事例だったと言えます。
耐用年数のルールが細かく複雑なのでこうなる訳ですが、違法な課税処分が必然的に起きてしまう、このような税法や税務行政を容認すべきではないでしょう。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs