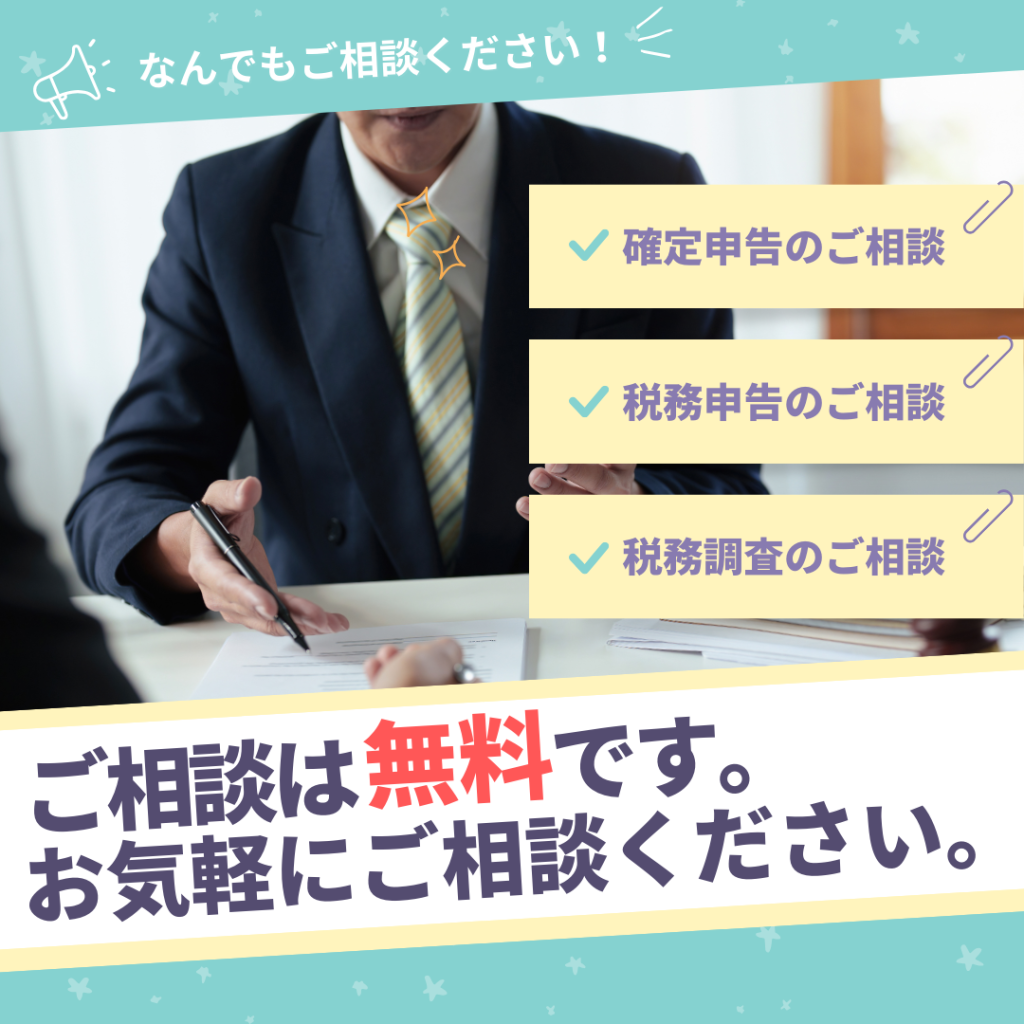電子保存義務化により保存すべき資料が増える
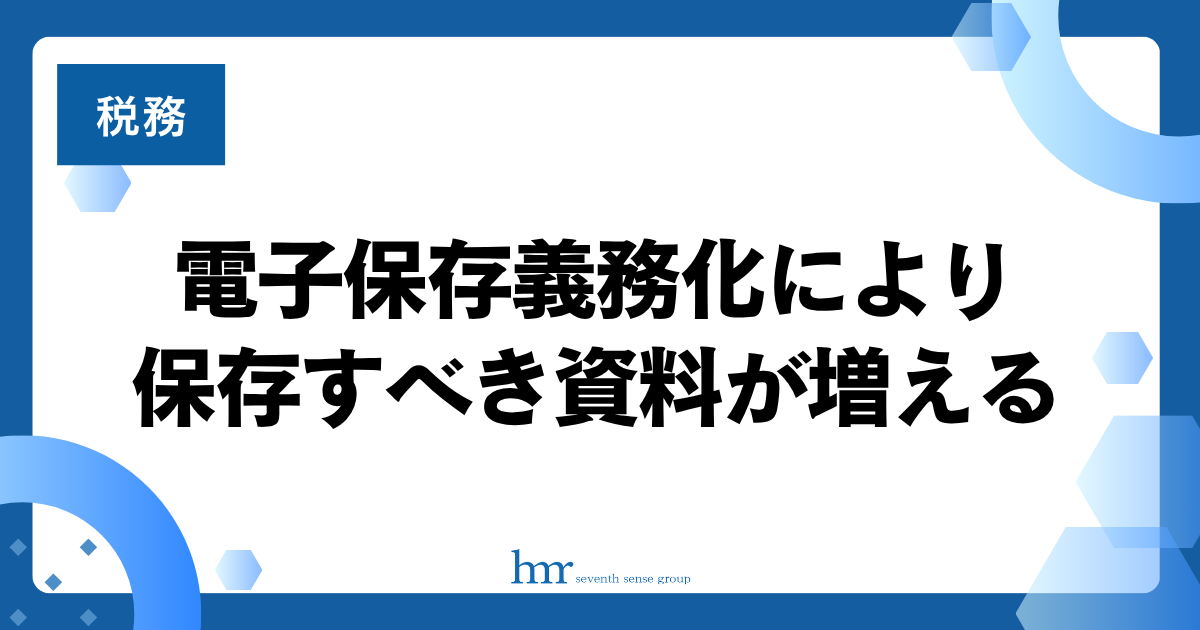
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第五百六回目。
テーマは、「電子保存義務化により保存すべき資料が増える」です。
電子取引のデータ保存の義務化がスタートしていますが、現実に即していない部分も大きいと思われます。
その一つに、保存すべき電子データの範囲が広すぎることが挙げられます。
以前相談を受けた事例です。注文を受ける際に送られる注文書、そしてその後送られる見積書、そしてその後の請求書や納品書、これらを電子データでやり取りしている場合、そのデータはすべて電子保存が必要かどうか質問を受けました。
大量の商品を数多くの顧客に売る商売ということもあり、すべて電子保存するとなるとあまりにも多くのデータを保存する必要があり、現実ではないという話でした。
しかし、法律を読む限り、すべて電子保存が必要である、としか言いようがありません。
この点、電子帳簿保存法は基本的に、紙で保存することを前提に作られている税法の保存資料を、紙に代えて電子で保存する場合の取扱いを定めたものです。
紙で保存する法人税の資料として、「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」と規定されています。
このため、そうなると見積書の控えなども含めこれらは全部保存しなければならない、という結論になるはずです。
しかし、これらの書類は、法律上紙で保存する義務があるとされていても、税務調査でこれら全部の確認がなされることはまずありません。
加えて、多少保存がなかったとしても、調査官は事実関係が確認できれば基本問題にしませんし、万一は反面調査をして内容を確認します。
何より、税務調査は時間が限られるものです。結果として、税務調査ではお金の流れに直結する請求書や領収書くらいしか見ないことがほとんどです。
このような事情がありましたので、改正前の電子データをプリントアウトして紙で保存していた時代には、資料の保存が雑であったり多少資料が不足したりしていても、問題が起こることは決してありませんでした。
しかし、新しく電子データでやり取りする場合には、そのデータを保存する義務がある、とされました。
この改正を機に、このようないい加減な状況も見直されるリスクがあり非常に厄介な状況と言わざるを得ません。
とりわけ、検索がしやすいというのが電子データの特色です。
調査官としては電子データの保存になると簡単に見たい資料を発見できる訳ですから、困るのはデータを大量に保存する義務がある納税者だけです。
いい加減だったかもしれませんが、従来のような、納税者の手間を強制しないことも実務では必要不可欠ですので、この点税務当局の柔軟な対応が今後とも期待されます。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs