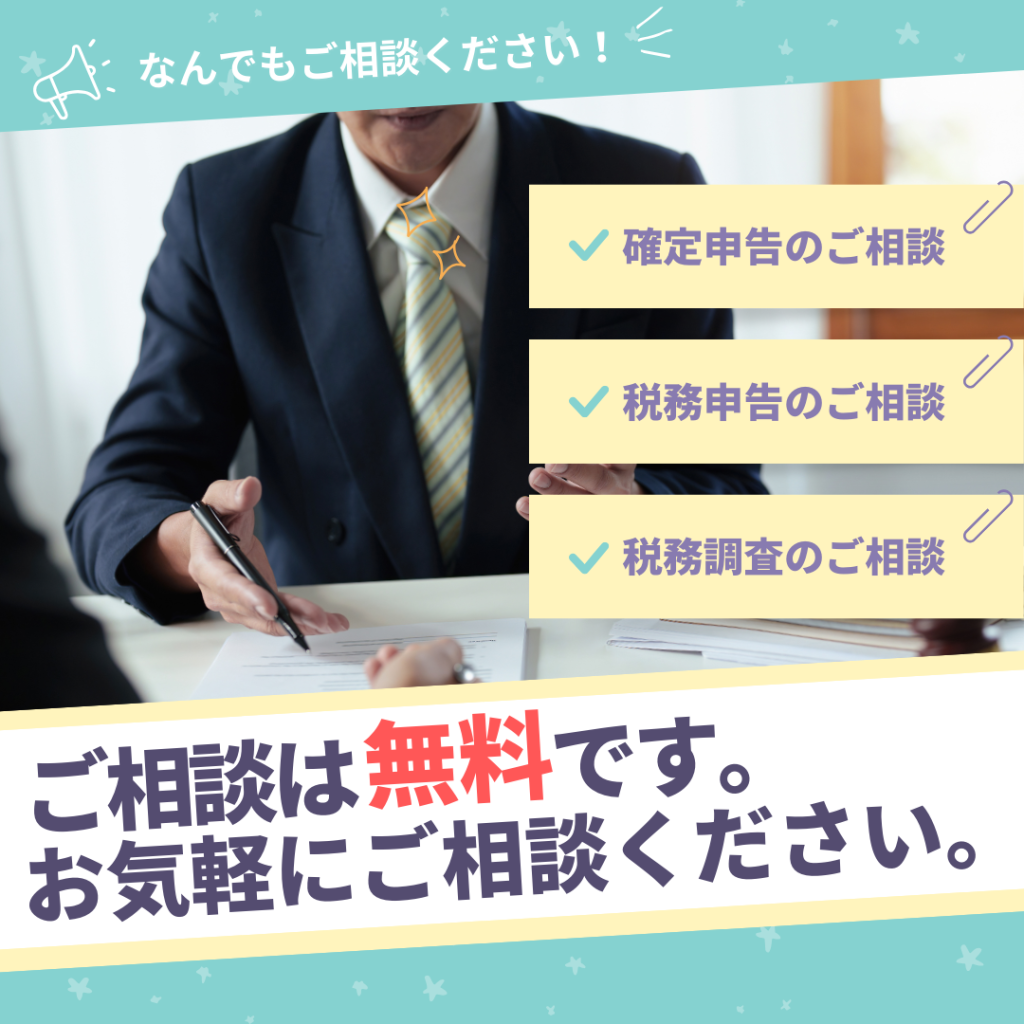形式基準と会社法
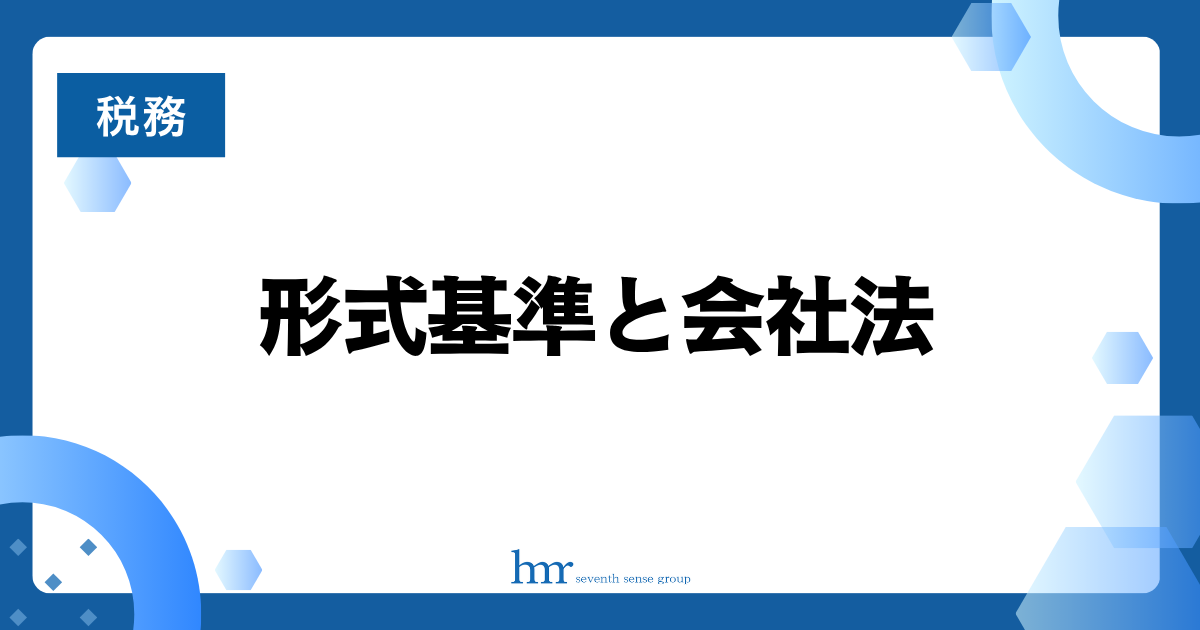
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第四百九十八回目。
テーマは、「形式基準と会社法」です。
税務上、批判が非常に多い過大役員報酬については、実質基準と形式基準の二つで判断されます。
前者は同規模・同業他社の支給金額などを前提に適正額を算定し、その適正額を超える役員報酬を過大役員報酬とする基準です。
理屈としてはよく分かりますが、同規模・同業他社の支給金額など一般の納税者はもちろん、税務当局も明確に判断できません。
このため、実質基準により過大役員報酬について課税されることは多くありません。
実務上、問題になるのは圧倒的に形式基準です。
これは定款などで役員報酬の限度額などを決めた場合、その限度額を超える部分を過大役員報酬とする基準です。
形式的に決まっている限度額を適正額とするため誰にでも分かります。
このため、仮にミスしてこの金額を超えた役員報酬を支給してしまうと、即座に過大役員報酬として課税されます。
困ったことに、限度額を定めたことを忘れるなど、実務では形式基準のミスが非常に多くあります。
このため、最も簡単でかつ確実な対策として、役員報酬について、限度額のような金額を定めないことが重要です。
このような定めがなければ、実質基準だけで判断されますので、過大役員報酬で課税されるリスクは小さくなります。
しかし、ここで問題になるのは、会社法上、毎期株主総会などで、役員報酬の金額や現物支給する内容を定めなければならないとされている点です。
ここで定められるべき金額や内容についても、当然ながら形式基準における限度額に含まれます。
すなわち、会社法上、限度額を定めることが義務とされるため、形式基準の適用を逃れることはできない、といった指摘があります。
確かに、会社法上役員報酬の金額は株主総会等で定めるべきとされているため望ましくはないことは事実です。
しかし、国税の内規を見ると、仮に定めがなければ形式基準の適用はしない、と明記されています。
つまり、税務当局としても定めがないケースを想定しているのです。
むしろ、中小企業は株主と役員が原則一致しますので、役員報酬について株主総会で特に定めないことも多いように思います。
しかし、それで問題になった事例は耳にしません。
なお、税務調査で役員の現物給与の課税漏れを指摘されることが多々あります。
この場合、会社は現物給与を支給したなどと思ってもいないため、株主総会で現物給与の内容を決議していません。
となると、建前としては会社法上問題があるはずですが、この点について問題視された事例も聞いたことはありません。
役員報酬の金額について、会社法の問題が生じるとはいっても、実務では基本的にはスルーされているのです。
むしろ会社にとって致命的な問題になる、税務調査対策を優先させるべきと考えます。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs