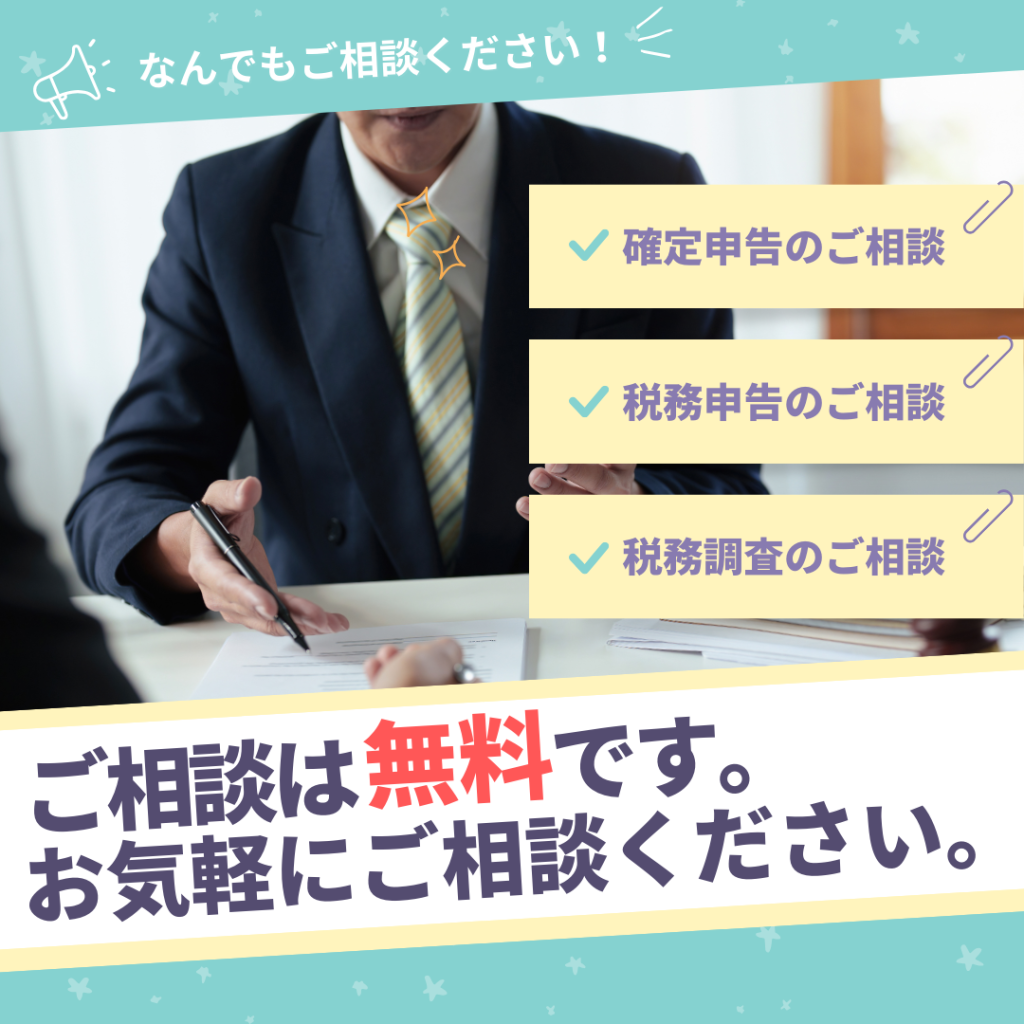未分割と葬式費用
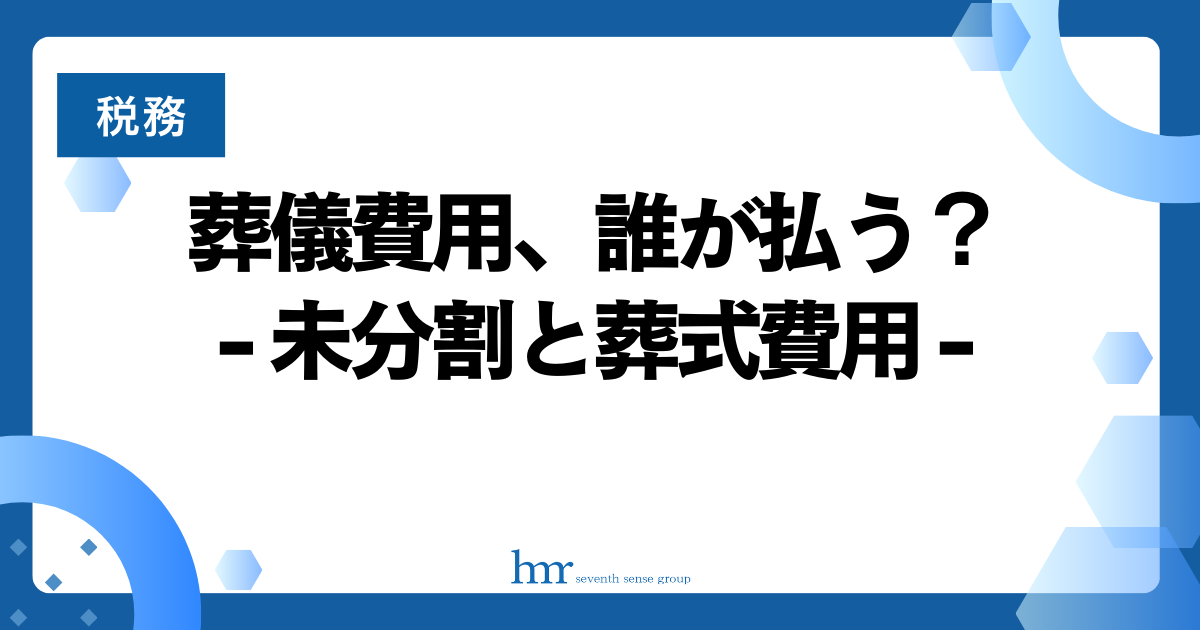
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第四百九十四回目。
テーマは、「未分割と葬式費用」です。
相続税の計算で混乱する論点として、負担者が決まっていない葬式費用の取扱いがあります。
相続人が負担する被相続人の葬式費用は、被相続人の債務と同様、相続財産から控除されます。
しかし、相続においては遺産分割協議がまとまらないことも多く、そうなると葬式費用についても誰が負担するのか、相続人間で決まらないことが多くあります。
大前提として、遺産分割協議がまとまらず相続財産が未分割であっても、相続税の申告はその期限内に行う必要があります。
この場合には暫定的に各相続人が法定相続分等に応じて財産を取得したものとして申告をすることとされています。
その上で、後日分割協議がまとまれば再計算をし、追加で相続税の納付をしたり還付を受けたりする、という取扱いとされていますが、葬式費用についてもこの取扱いと同様でいいのか、疑義があります。
民法の判例上、葬式費用については、相続人間で合意がない場合、追悼儀式の費用は葬儀の主催者である喪主が負担し、埋葬費用は遺骨等を管理する祭祀承継者が負担する、といった取扱いになっているようです。
葬儀費用については、死亡後に発生するものですので法の建前としては遺産分割協議の対象にはならないことから、負担について相続人間で話し合うことはできても、法定相続分等で負担するということにはならないと言われます。
その一方で、相続税の裁決事例を検討すると、先の判例とは逆で、負担者が決まっていなければ後日負担者を決めるため、法定相続分等で按分した上で各相続人が控除するべきとされたものがあります。
困ったことに、民法の判例と同様に、喪主が負担するべきと解釈された事例もあり、実務においてどのように整理をするべきか、疑義があります。
この点、喪主が負担するべきとされた事例を検討しますと、喪主が葬儀費用について、他の相続人に求償するつもりはない、と税務当局に回答していることが分かります。
その上で、求償するつもりがないなら、負担者は喪主でしかありえないので、喪主が葬儀費用のすべてを自己の相続財産から控除することができると判断されています。
一方、法定相続分等で按分するべきとされた事例は、葬式費用を誰が払うか争っており、負担者は確定していないと判断されています。
すなわち、民法の判例はあるにしても、相続税の計算上は喪主や祭祀承継者が負担すると単純に判断することなく、きちんと事実関係を確認した上で負担者が確定しているのか否か、確認する必要があると解されます。
葬式費用に限った話ではありませんが、結論だけを暗記することなく、事実関係を正確に確認し、慎重にそれを法律や判例に当てはめていく姿勢が、税務では重要と言えます。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs