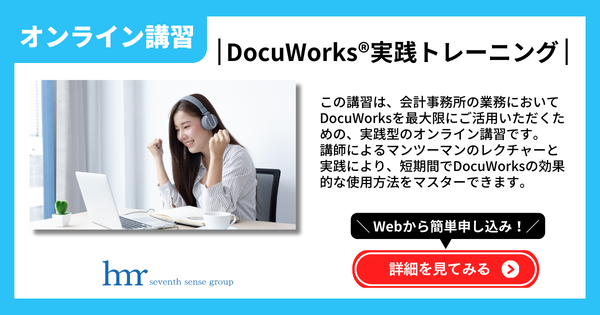前捌きによるスキャンの難しさ『ペーパーレスの壁』第2回
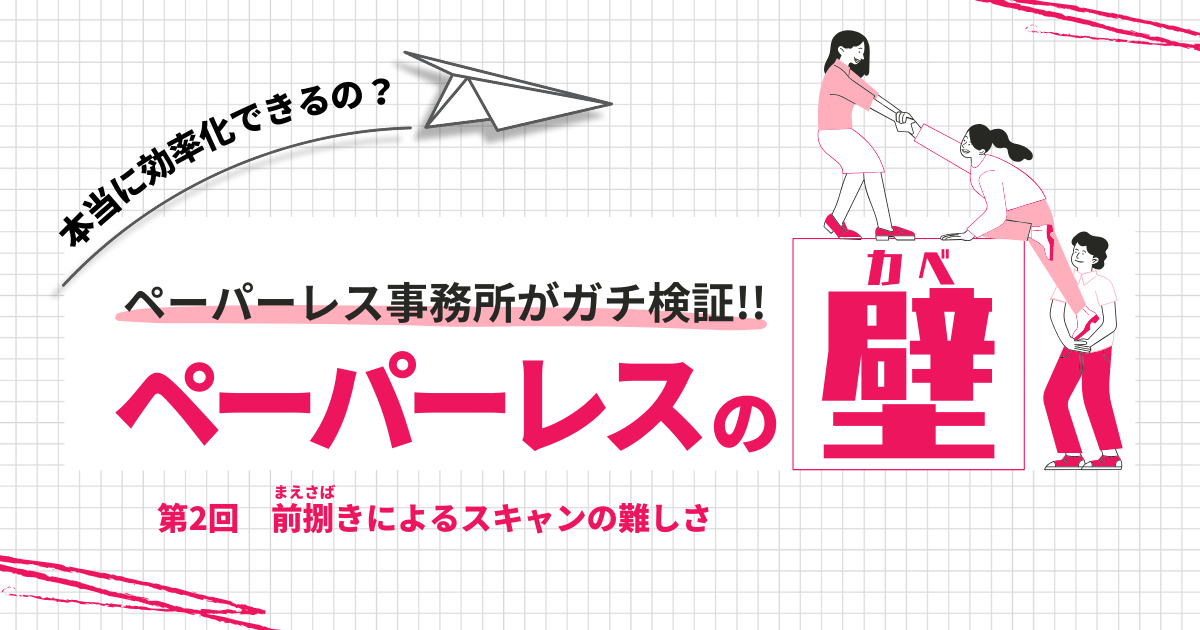
会計事務所にとって、業務の効率化は常に大きなテーマ。その中でも「ペーパーレス化」は、多くの事務所が取り組みたいと考えている施策のひとつです。前回のコラムでは、回収した資料の状態が、回収資料のスキャンを阻む要因になっていることを取り上げました。
今回のコラムでは、スキャン業務を分業するにあたって問題となる“前捌き”に焦点を当て、その難しさと業務構築の課題について検証していきます。
🔍会計事務所・ペーパーストックレス・DX・スキャン・資料管理
…これらのワードに「おっ‼👀」となった方、必ず最後までご覧ください!!!

2010年アイクスグループ (現 セブンセンスグループ) 入社。 システム部門で採用され、社内サポートおよび年末調整や確定申告などの季節業務の企画・運営を担当。
2015年より、会計事務所向けにペーパーレス化の仕組みを指南するPSL(ペーパーストックレス)コンサルティングに携わる。
現在は、会計事務所専任コンサルタントとしてPSL導入支援やDocuWorksのセミナー講師、kintone管理者サポートを行っている。
スキャン工程の構築を阻む壁
セブンセンスではかつて、「顧問先から預かった資料をスキャンする」という業務を、各担当者の手から分離し、専任の業務工程として切り出す試みを行いました。その際、大きな壁となったのが「前捌き処理」でした。
当時のセブンセンスは、会計データの入力を遠隔拠点で行う体制の構築を推進しており、その前提として、顧問先から受け取った資料をスキャンによって電子化する運用を開始していました。

ところが、各担当者は顧問先から資料を預かっても、すぐにスキャンに取りかからず、資料が手元に滞留するケースが多く発生しました。結果として、業務がスムーズに流れないという問題が顕在化していったのです。
こうした滞留を解消するために、セブンセンスではスキャン業務を独立させ、専任の部門が実施する体制に切り替えることになりました。資料の電子化を担当者ごとの個別作業ではなく、標準化された業務工程として切り出すことで、業務全体のスピードアップと均質化を図る狙いがありました。
しかし、ここで新たな課題が浮かび上がります。
それが、「前捌き(まえさばき)」と呼ばれる処理の存在です。
前捌き処理とは、顧問先から受け取った紙資料をスキャン前に分類・整理し、不足資料を見つけ出したり、後の会計入力がしやすくなるように整える工程を指します。従来は、顧問先の事情をよく理解した各担当者が、「前捌き」→「スキャン」という順番でこの作業を行っていました。
ところが、スキャン部門の担当者は、各顧問先の業種や取引の特性、必要な資料の傾向を把握していません。そのため、どの資料が会計データとして重要なのか、何が不足しているのか、どの順番で整理すると効率が良いのかを判断することができませんでした。
このような状況では、前捌き処理をスキャン部門に移管することは現実的ではなく、結果的に業務の切り分けが進まないという問題に直面しました。そこで、発想を転換し、「スキャン」→「前捌き」という順番に業務フローを変更するという決断を下すことになったのです。
「スキャン→前捌き」という流れに切り替えたことで、業務の分業体制はひとまず機能するようになりました。しかし、この変更にともなって新たに2つの問題が浮かび上がります。
ひとつ目は、「不要な資料まで大量にスキャンされてしまう」という点です。資料を分類せずに丸ごとスキャンすることで、必要のない書類まで電子化されることになり、その分だけ作業工数が増えてしまう懸念がありました。これでは、かえって担当者が個別にスキャンしていたときよりも非効率になる可能性があります。
ただし、この問題については時間とともに改善が進みました。スキャン業務が専任部門に集約されたことで作業の習熟度が高まり、結果として各担当者が個別に行うよりも効率よく処理が可能になったのです。加えて、スキャン部門が必要な資料のリストを整備し、スキャン前に明らかに不要な資料をある程度除外できる体制も構築され、問題の大半は解消されました。
そしてもうひとつの問題が、「スキャンされた資料を、担当者がPC上で効率よく前捌きできるかどうか」という点です。紙であれば資料を手に取りながら直感的に分類できますが、電子化された資料を画面上で扱うとなると、操作性や閲覧性の課題が生じ、かえって作業に時間がかかってしまう恐れがありました。
この課題に対しては、自社で開発した「資料振分ツール」を導入することで解決しました。このツールにより、電子化された資料を効率的に分類・確認できるようになり、前捌き作業のPC上での再現性が飛躍的に向上しました。
さらに、資料のリスト化とツール活用の定着によって、前捌き処理そのものも分業できる体制が整い、専任部門による対応も可能になっていきました。
どの資料が不足しているかも一目瞭然。詳細はこちらの記事から
とはいえ、この前捌きの問題は、すべての事務所で簡単に解消できるものではありません。特に、スキャン業務の専任体制やツール環境が整っていない場合、前捌きの効率は大きく変わってくると考えられます。
そこで本コラムでは、こうした体制が整っていない事務所を想定し、資料の前捌き処理にどの程度の手間がかかるのかを検証していきたいと思います。
現物と電子化資料、それぞれの“前捌き”にかかる時間とは?
前捌き処理を分業する際、実際にどれだけ手間がかかるのか?
——この疑問を解明するため、私たちは検証を行いました。
今回の検証では、ひとつの顧問先から預かった資料をサンプルとして選定し、以下の2パターンで前捌き作業にかかる時間を測定しています。
- 現物資料を手作業で前捌きする方法
- スキャン済みの電子資料(DocuWorksファイル)を使い、ツールなしで前捌きする方法
サンプル資料の概要
- 総枚数:85枚
- 分類する資料リスト:21種類
- 資料の状態:種類ごとに整っておらず、サイズはバラバラ。ホチキスで綴じられている資料も混在。レシート類は含まれていない。総合振込による請求書の束も、ひとまとめにされているような状態。
実施条件
- 各パターンの分類対象は、用意された資料リストに沿って行う。
- 検証スタッフは1名。当該顧問先を通常担当している人物ではなく、高度な税務・会計知識もないので、あくまでリストに頼って資料の「振り分け」のみ行う形式で実施。
- 現物資料による振り分け作業を先に実施し、その後に電子資料による作業を実施。
頑張ってもらいました。
検証結果
それぞれの作業パターンでかかった時間は以下の通りです。
- 現物資料での前捌き:33分52秒
- 電子資料での前捌き(ツール未使用):28分56秒
現物資料の方が、ホチキス留めの解除や紙の並べ替え、スペースの確保といった手間が多く発生する分、やや時間がかかる結果となりました。一方で、電子資料を使った前捌きは、ソフトの操作に一定の慣れが必要なものの、物理的な処理が不要な分時間短縮につながっていると考えられます。
ただし、いずれのケースにおいても担当者は当該顧問先の情報に明るくないため、資料リストと照らし合わせながらの作業となり、それなりの時間を要することが分かりました。
📝参考メモ「専任部門による処理時間」
なお、同じ資料をセブンセンスのスキャン専任部門(資料管理課)で処理した場合、作業時間はおよそ10分という記録が残っています。
※この記録は業務システム上で担当者が自己申告により記録した実務データです。
この作業には、自社開発の「資料振分ツール」が使用されており、資料の種類や内容を一覧しながら効率的に分類できる環境が整っています。加えて、部門として同様の処理に日常的に慣れていることも、作業スピードを押し上げる要因になっていると考えられます。
検証から見えてきた、前捌き業務のリアル
今回の検証では、あくまで「その顧問先に詳しくない担当者」が前捌き処理を行ったケースであり、顧問先の業務や資料構成に精通している担当者であれば、さらに短い時間で処理できる可能性は十分にあります。
また、分類の細かさにも影響があったと考えられます。セブンセンスでは、会計データの入力を特定の担当者に固定せずチームで回す体制をとっているため、「誰が見ても分かるように」という基準で、比較的細かく資料を分類する運用になっています。分類基準が細かければ、その分処理時間も長くなります。
とはいえ、そうした前提条件を差し引いたとしても、現物・電子資料のいずれにおいても、前捌き処理には相応の時間がかかることは間違いありません。
実際に検証を担当したスタッフからは、次のような感想がありました。
現物資料のみで振り分けを行う場合、資料リストに沿って項目ごとに分ける必要があるため、とにかく広い作業スペースが必要になります。また、クリアケースごとに束ねられて受領した資料を、元の状態を崩さずに分類していくのが非常に難しいと感じました。
一方、電子資料(DocuWorksファイル)での分類については、次のようなコメントもありました。
一見すると、現物のみよりスムーズにできそうに見えるのですが、資料を整理するためのフォルダーを複数開いて処理する必要があるため、普段使っている2画面では画面が狭く感じました。4画面くらいあると快適に作業できる印象です。
今回の検証では、こうした実感もふまえて、できる限りDocuWorksの機能を駆使して処理を進めましたが、ソフトの仕様上の限界があるため、大幅な効率化にはつながらない印象でした。
その一方で、検証を通じて改めて実感したのが「資料のリスト化」の効果です。
リストがあることで、担当者はその内容に沿って分類を進めることができ、資料の知識がなくても一定の精度で処理が可能になります。これは、業務の分業を進めるうえで非常に大きな要素であり、不足資料の早期発見にもつながる重要な仕組みだといえます。
加えて、過去の資料がそのリストに従って整理された状態になっていることで、顧問先の担当者以外でも、過去資料を参照して資料振り分けの作業が行えるようになるというのは、電子資料であることの大きなメリットといえそうです。
業務を分けるからこそ、“共有の設計”が鍵になる
今回の検証を通じて明らかになったのは、前捌きという工程が単なる「分類作業」ではなく、業務全体の流れと密接に結びついているという事実です。
資料が現物であれ電子であれ、「誰が・どのように・何を基準に分類するのか」が曖昧なままでは、分業によってかえって非効率になるリスクすらあります。一方で、資料のリスト化やツールの導入といった“共通の土台”が整えば、担当者の知識や経験に依存しすぎることなく、安定した分業体制を築くことができます。
業務の分業とは、単に作業を「ばらす」ことではなく、「つなぐ」ことでもあります。
そのためには、前工程と後工程の間にある“意図の共有”や“整理の設計”が極めて重要です。
資料を分類するという、地味で細やかな作業。
けれども、それをどう仕組み化するかが、結果として業務全体のスピードや品質を大きく左右します。
このコラムが、貴事務所での業務体制の見直しや改善のヒントになれば幸いです。