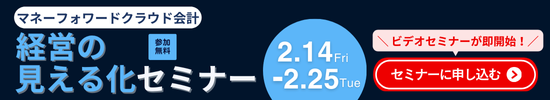東先生の人事労務相談室「企業が取り組むべき不妊治療支援の対策とポイント」
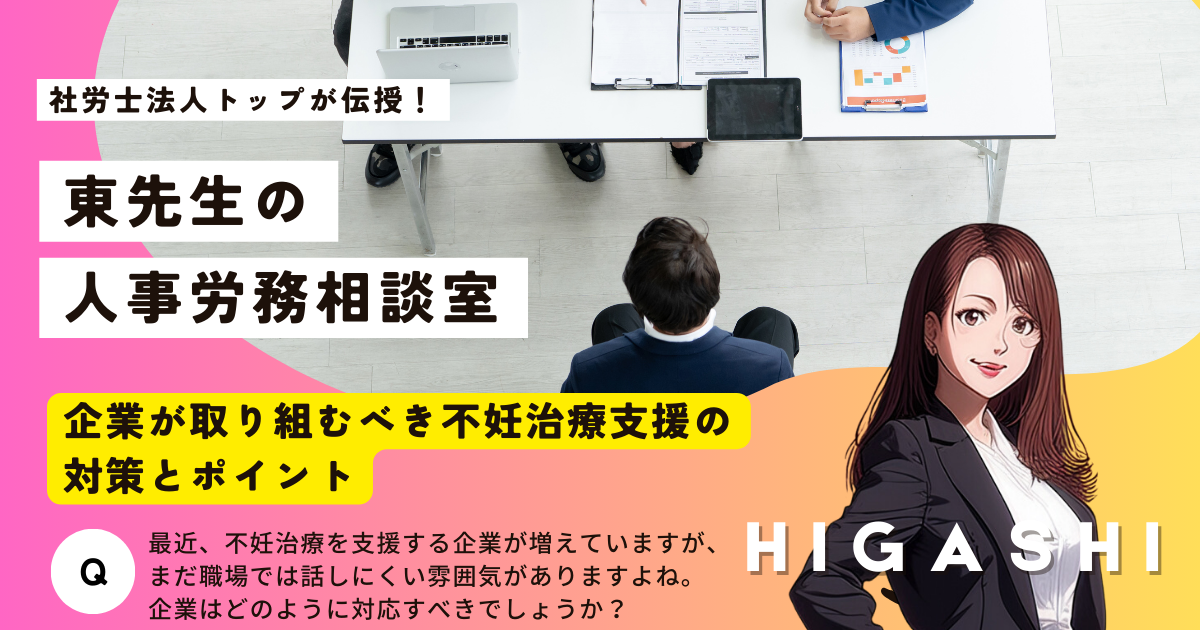
社会保険労務士の東先生が、これまでの豊富な経験をもとに、人事労務に関するさまざまな疑問にわかりやすくお答えします。今回は、不妊治療と仕事の両立を支援する職場づくりについて。治療を続けながら働くことの難しさや、企業が取るべき支援策について解説します。職場の理解や制度の整備が進めば、従業員がより安心して働ける環境につながるはず!
今回はどのようなアドバイスが聞けるのでしょうか?教えて東先生!

セブンセンス社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 代表社員

「最近、不妊治療を支援する企業が増えていますが、まだ職場では話しにくい雰囲気がありますよね。
企業はどのように対応すべきでしょうか?」
不妊治療は、職場の理解不足で、治療を続けづらくなるケースも…。
企業が取り組むべき具体的な支援策について、一緒に考えていきましょう!

不妊治療と仕事の両立における課題
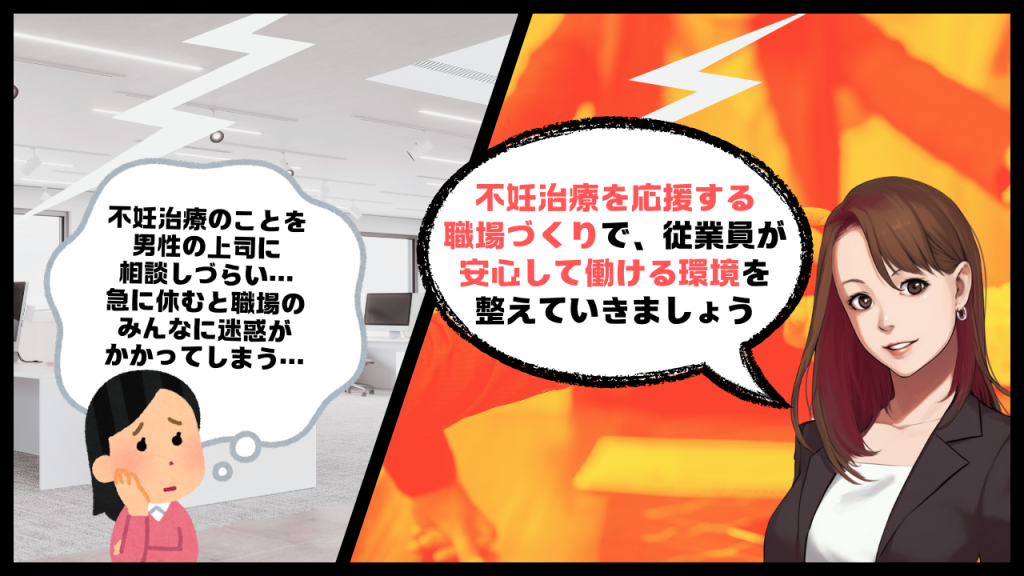
不妊治療と仕事を両立するには、いくつかの課題があります。特に、治療の進行状況や体調によって通院のタイミングが変わるため、従業員が事前にスケジュールを調整することが難しいのが現状です。そのため、職場に迷惑をかけるのではないかという不安を抱え、治療を続けることにプレッシャーを感じるケースもあります。
また、不妊治療は長期にわたることが多く、思うような結果が出ないことで精神的なストレスが蓄積し、不妊治療の継続に影響を及ぼすことがあります。職場での理解が十分でない場合、治療を公表しづらく、孤独感や精神的負担がさらに増大する可能性があります。さらに、職場全体での理解が不足していると、急な休暇や勤務調整が受け入れられにくく、周囲の目を気にして治療を断念せざるを得なくなるケースも少なくありません。
企業が取るべき支援策
不妊治療を受ける従業員を支援するために、企業にはいくつかの対応が求められます。まず、通院や治療スケジュールの変更に柔軟に対応できるよう、不妊治療に対応できる休暇制度(特別休暇や時間単位の有給休暇の導入)やフレックスタイム制、在宅勤務の活用が重要です。休暇制度を設けることで、従業員は治療と仕事を両立しやすくなり、離職を防ぐことにもつながります。
急な休暇が必要になった場合に備え、業務の引き継ぎ体制を整えておくことも重要です。治療内容を詳しく説明しなくても済むよう、「体調不良による休暇」などプライバシーに配慮した情報共有の仕組みを作ることで、周囲の理解を得やすくなります。
また、不妊治療に関する相談窓口を設置し、従業員が適切な情報を得られるようにすることも有効です。専門家によるカウンセリングの提供や、助成金制度の案内を行うことで、不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えることができます。
不妊治療を支援する制度と助成金の活用
不妊治療を受ける従業員を支援するため、国も助成金制度を設けています。企業が不妊治療と仕事の両立を支援する制度を導入し、従業員が実際に利用した場合、両立支援等助成金「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」を受給することが可能です。この助成金を活用することで、企業側の負担を軽減しつつ、制度を整備することができます。
助成金の申請には、支給要件の確認や必要書類の準備が必要なため、社労士に相談することが有効です。適切な制度設計を行うことで、従業員が利用しやすい環境を整えることができるでしょう。
まとめ
不妊治療を応援する職場づくりは、従業員が安心して働ける環境を整えるだけでなく、企業の魅力向上にもつながります。休暇制度の整備や柔軟な働き方の導入、職場の理解促進を進めることで、従業員の負担を軽減し、従業員の安心感や働きやすさが向上し、結果として定着率や生産性の向上につながる可能性もあります。今後、ますます多様な働き方が求められる中、不妊治療支援を含めたワークライフバランスの向上に取り組んでいくことが重要です。
▼ 人事に関するトラブルのご相談はバナーから ▼
▼ 録画セミナーなので期間中何度も視聴可能!経営の見える化セミナー 開催! ▼