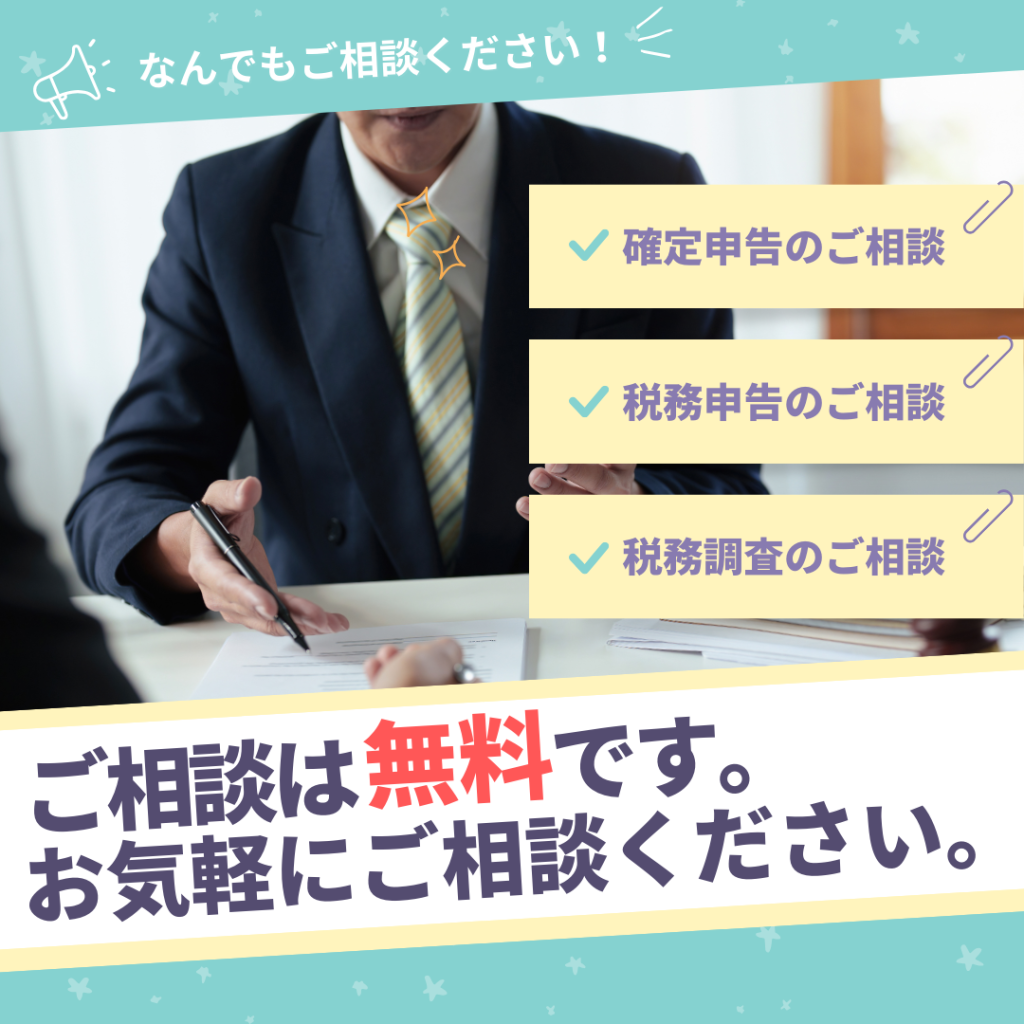「消費税は預り金ではない」を重視すべきではない
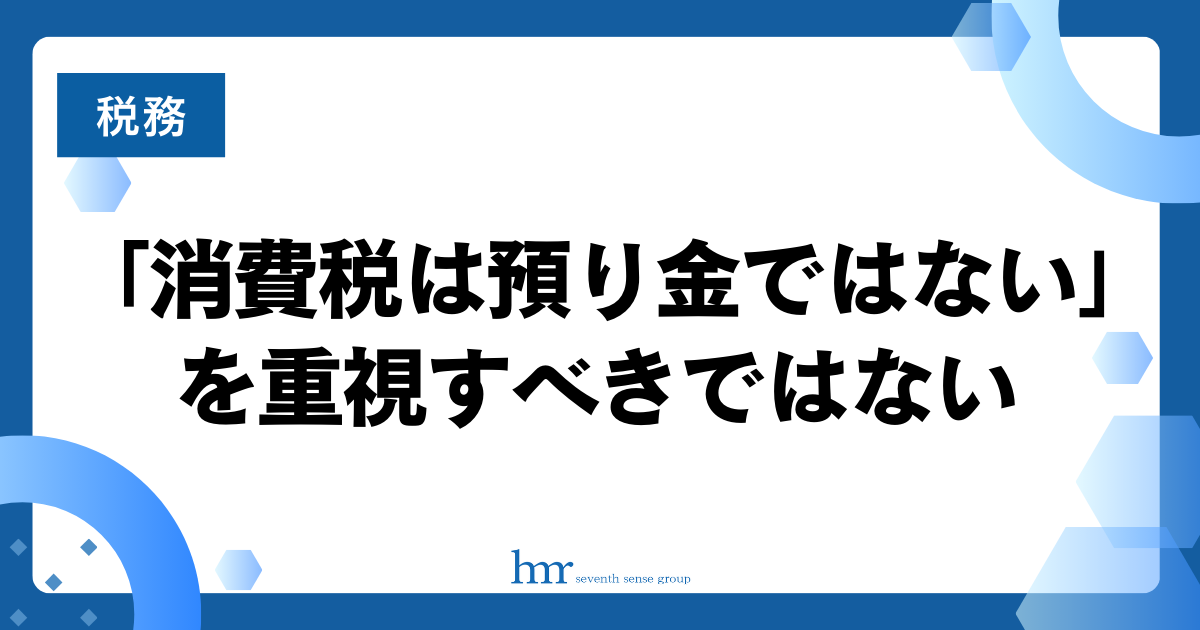
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第四百八十二回目。
テーマは、「『消費税は預り金ではない』を重視すべきではない」です。
未だに反対意見が多いインボイス制度ですが、王道的な反論として、「消費税は預り金ではない」という指摘があります。
消費税は消費者から預かって納付するものではないので、インボイスで消費税を明示する必要もない、というのがこの理屈です。
消費税は預り金でないという意味ですが、これは消費税法上「消費者から預かった消費税を納税する」という規定はないことを意味しています。
実際、消費税法では、「事業者が売上としてもらった金額の10/110を消費税として納税する」とされているのです。
自分の売上金額から逆算して消費税を納める訳ですから、消費者から預かっていない訳で、仮に税抜で販売してしまったとしても、その事業者は税抜金額を10/110した消費税を納めなければなりません。
この点を踏まえ、税務当局も消費税は預り金「的」な税と説明しています。
このため、法律だけを見れば、消費税分上乗せで請求しているのに、消費税が免税されるという理由で消費税を納めない免税事業者の「益税」問題もないことになります。
預かった消費税の納税を免除されて儲かった、ということは生じないからです。
このため、消費税は消費者から預かっていないため、インボイスで消費税を明記する必要はなく、結果としてインボイスもいらない、というのが反対派の意見なのです。
しかし、消費税は法律の建前は別にして、理論としては預り金として取り扱うべきと考えています。
なぜなら、自分たちが負担した消費税を事業者が預っている、と消費者には思ってもらわないと、事業者が消費税分上乗せで代金請求することが困難だからです。
消費税を預けているという意識があるからこそ、消費税増税の際に行われる事業者からの値上げも消費者は受け入れます。
とりわけ、消費税は価格に消費税分を上乗せして取引する「転嫁」が適正になされなければ、機能しない税金です。
加えて、法律上消費税を預かり金としてしまうと、消費税を納めるべき事業者が消費税を消費者から預り忘れて、税抜きで売ったような場合には徴税ができないことになります。
消費税分上乗せして顧客に請求しているのに、消費税を預かっていないから納税もできない、などと嘘をついて課税を免れようとする納税者が増える可能性もあります。
これらの点を踏まえ、一般の消費者の方には預り金と考えてもらうものの、徴税などの便宜から法律では預り金としていないのが消費税の位置づけと思われます。
法律の建前だけを取り上げて、「消費税は預り金でないのでインボイスはいらない」「消費税を預り金と勘違いさせられ、益税問題があると騙されている納税者が存在する」といった解説もなされることがありますが、税の理屈としては適切ではないように思われます。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs