東先生の人事労務相談室「賃金改定時の注意点」
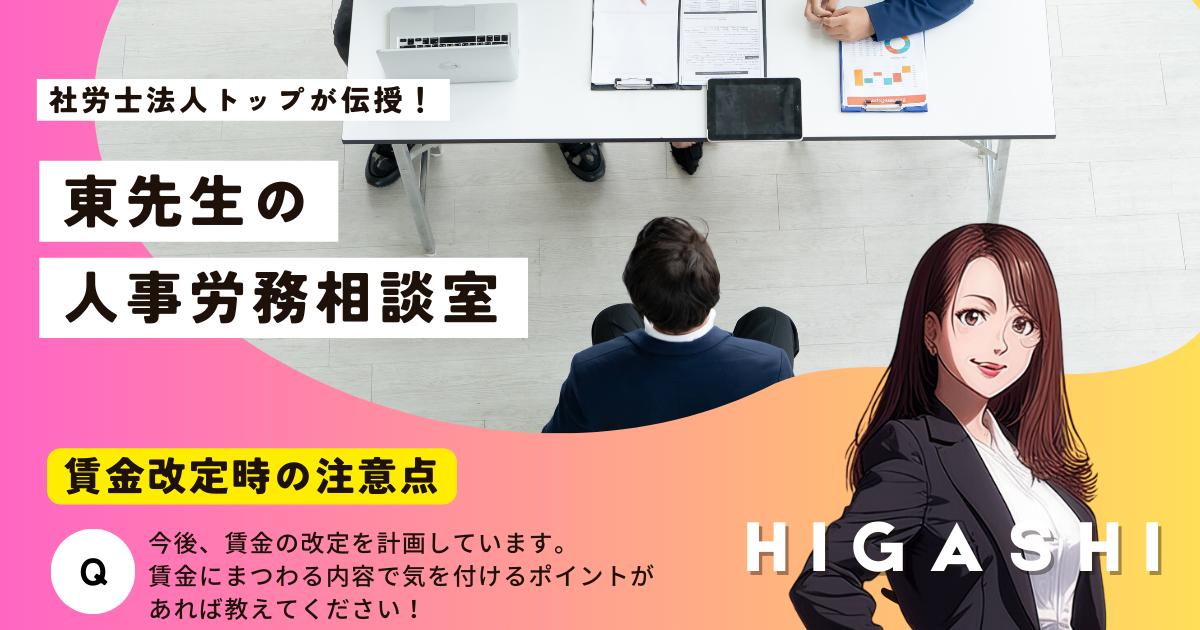
社会保険労務士の東先生が、これまでの豊富な経験をもとに、人事労務に関するあらゆる質問にわかりやすくお答えします。ハラスメントや労務管理の課題など、職場環境の改善に直結するトピックスが満載です。これを読めば、よりよい職場環境づくりに向けて、すぐに役立つ知識を得ることができるはず!今回はどのような質問に答えてくれるのでしょうか?教えて東先生!

セブンセンス社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 代表社員

「今後、賃金の改定を計画しています。
賃金にまつわる内容で気を付けるポイントがあれば教えてください!」
賃金は法律で厳格に守られています。
社内で知識を得ることも重要ですが、
実際の対応時には専門家に相談をしたほうが確実でしょう!

賃金引き下げ時の注意点
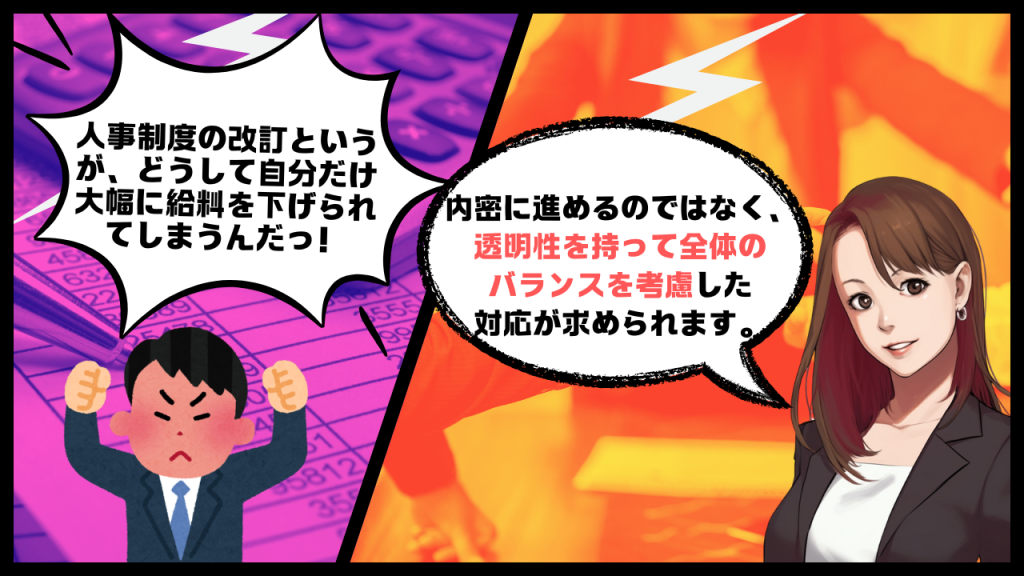
昨今の最低賃金の引き上げに伴い、賃金の増額は一般的に問題を生じにくいですが、逆に賃金を引き下げる場合、労働者の納得を得ることが難しく、トラブルに発展するケースが多くあります。
特に、人事制度の改訂に伴う基本給の変更で、特定の労働者のみ賃金が大幅に変動する場合、公平性の観点から不満が生じやすくなります。このような場合、内密に進めるのではなく、透明性を持って全体のバランスを考慮した対応が求められます。
会社の規程である人事評価制度の評価に基づいて降格や減給を行う場合でも、不利益変更にならないよう、本人に合理的なものであることを説明し、合意してもらえるよう事前に協議しましょう。(3年~5年で段階的に減額する方法を行う会社も多いです)
懲戒処分としての減給の制限
また、懲戒で減給を行う場合、法律で細かなルールが定められていることをご存知でしょうか。
労働基準法第91条では、懲戒処分としての減給に関する制限が定められています。具体的には、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以下、かつ減給の総額が賃金総額の10分の1以下でなければなりません。
(例)月給20万円(日給1万円)の社員の場合
1回の減給額は「平均賃金の1日分の半額以下」のため、上限は3,333.33円
「減給の総額が賃金総額の10分の1以下」のため、1回の賃金支払における上限は2万円
これらの制限を超える減給は違法となるため、懲戒処分を行う際には、就業規則に基づき、適切な手続きを踏むことが重要です。また、減給処分は一度限りであり、複数月にわたって継続することは認められていません。
専門家への相談の重要性
前段では「懲戒処分の減給」を例に挙げましたが、賃金関する法律が多くあります。
例えば、労働基準法第24条では、賃金の支払いに関して5つの基本原則を定められています。
それぞれ原則として…
(1)賃金は現金という通貨で支払わなければならず、現物支給は認められません。
(2)支払いは必ず労働者に直接行う必要があり、代理での支払いは許されません。
(3)法定の控除以外は全額を支給しなければなりません。
(4)毎月1回以上の定期的な支払いが義務付けられています。
(5)支払い日はあらかじめ定められた一定の期日で行われる必要があります。
この条文は、労働者の権利保護と生活基盤の確保を目的としており、企業は厳守する義務があります。
(参考: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html )
自社での知識習得も重要ですが、賃金に関する法律は非常に複雑であり、違反すると企業にとって大きなリスクとなります。特に、賃金制度の改訂や懲戒処分を行う際には、法令遵守と労使間の円滑なコミュニケーションを図る上でも、労働基準法や関連法令に精通した社会保険労務士などの専門家に相談するを強くお勧めします。
まとめ
賃金の改定は、法令を厳守し、労働者の納得を得るための丁寧な対応が求められます。また、賃金制度の改訂やトラブル防止のためには、専門家の助言を積極的に活用し、適切な手続きを進めることが不可欠です。賃金に関する問題を慎重に取り扱うことで、労働者の安心感と職場の健全性を高め、企業の持続的な成長を支えていきましょう。
▼ 賃金に関するトラブルのご相談はバナーから ▼
