岩見先生の採用対策室「入社後のミスマッチを未然に防ぐためには?」
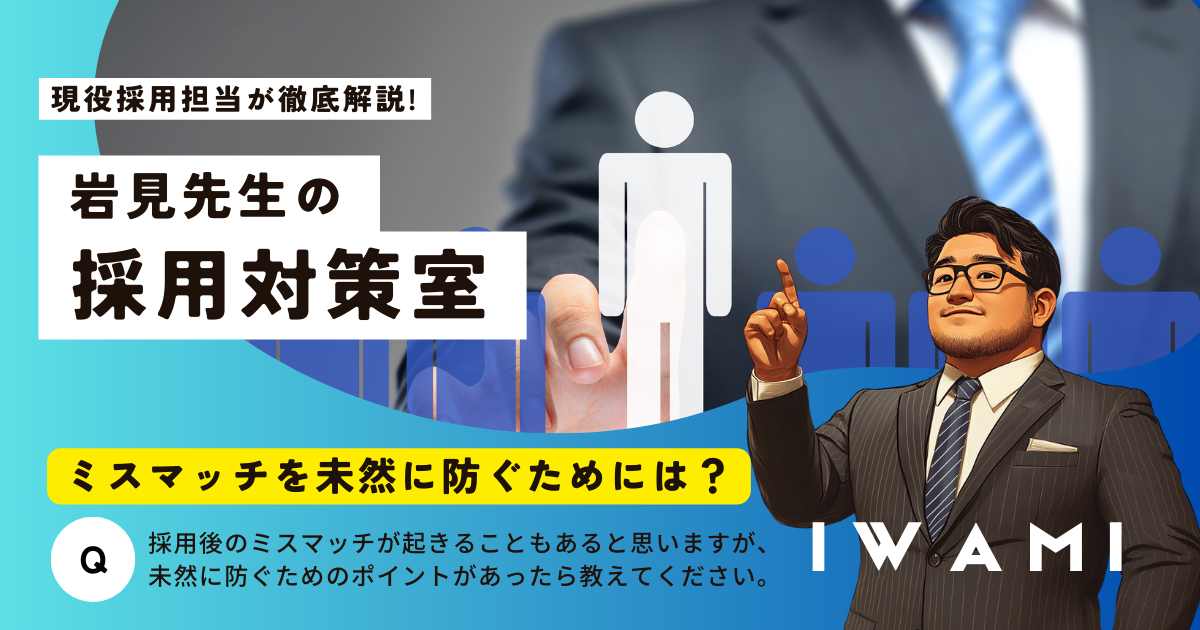
セブンセンスグループの現役採用担当であり、豊富な知識と経験を持つ岩見先生が、企業の採用活動における疑問に徹底的にお答えします。実務担当者だからこそ語れる「成功する採用活動」の秘訣や、実践的なアドバイスを通じて、皆さまの採用活動に役立つ情報を提供します!今回はどのような質問に答えてくれるのでしょうか?教えて岩見先生!

セブンセンス株式会社 総務部 採用課
出身地:東京 趣味:魚釣り・キャンプ
大学を卒業後、小売業界へ就職。5年間販売の業務に携わった後、本社へ配属となり採用担当を約10年間経験。2022年からセブンセンスグループの新卒および中途採用の業務に従事。

「採用後のミスマッチが起きることもあると思いますが、
未然に防ぐためのポイントがあったら教えてください。」
ミスマッチはコミュニケーション不足が原因となるケースがほとんどです。

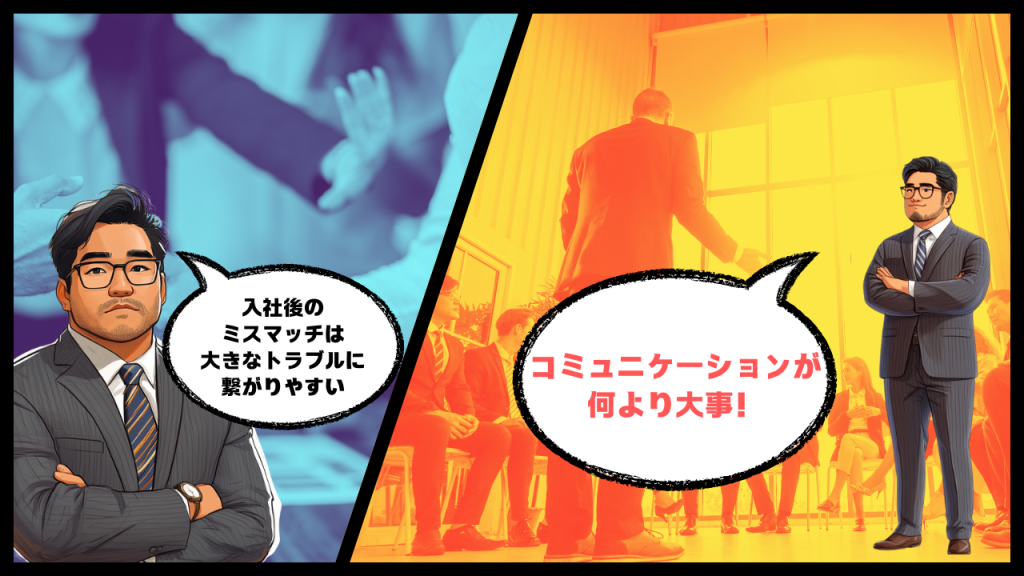
ミスマッチを未然に防ぐための採用のポイント
採用活動において、応募者と企業との間で起きる「ミスマッチ」は、離職の主要な原因の一つです。「聞いていた内容と違った」「思っていた環境と違う」といった理由で退職に至るケースは、企業にとっても応募者にとっても大きな損失になるでしょう。
しかし、事前に適切な対応を取ることで、これらのミスマッチを未然に防ぐことが可能です。本コラムでは、採用の段階でできる工夫と、入社後のフォローに焦点を当てて解説します。
採用前の透明性を高める工夫
採用活動でミスマッチを防ぐためには、応募者とのコミュニケーションにおいて透明性を持つことが重要です。以下のことを少し意識するだけで、応募者との関係性が大きく変わることでしょう!
- 企業の自己紹介の徹底
面接が応募者から志望動機を聞くだけの場になってしまうと、相互理解が深まらず、ミスマッチの原因となります。企業側からも「自社が、どのような会社で・どのような状況で・どのような仲間を求めているのか」を積極的に伝えることが重要です。このようなコミュニケーションは、応募者に企業の価値観やビジョンを共有することに繋がり、共感が生まれやすくなり、採用後のトラブルを未然に防ぐことができます。相互のコミュニケーションを大切にし、「キャッチボール」のような面接を心掛けましょう。 - 待遇面の明確化
採用活動における大きな課題の一つは、「給与」「賞与」「手当」「評価基準」「昇給制度」「福利厚生」などの待遇面を正確に伝えることです。これらについて、面接官が適当な回答をしてしまうと、応募者に誤解を与え、入社後の不満につながる可能性があります。そのため、面接官は待遇に関する情報をしっかりと理解し、正確に伝える準備を整える必要があります。特に、これらの情報を一覧表にまとめておくと、面接時に簡単に確認でき、誤解を防ぐのに役立ちます。 - 働き方や社風の適切な伝え方
採用難の状況が続く中、どの企業も一人でも多くの応募者を集めたいという思いが強まっています。しかし、働き方や社風を過剰に良く見せることは、かえって企業にとって大きなリスクを伴います。現代ではSNSが広く普及しており、企業が発信した情報が瞬時に拡散される時代です。実際に入社後のミスマッチで退職した元社員によるSNSの投稿が炎上し、会社の経営に深刻な影響を与えた事例もあります。
こうしたリスクを回避するためには、自社の現状を正確に伝える透明性が欠かせません。応募者が安心感を持てるよう、実際の働く環境を具体的に示すことで、応募者の理解を深めることができます。一方で、すべてを正直に伝えるだけでなく、自社の魅力を効果的にアピールする工夫も重要です。「風通しが良い職場」という表現を使う場合には、具体的な事例や根拠を添えることで、応募者に現実的かつ信頼できるイメージを持たせましょう。リアルな情報と魅力的なアピールのバランスを取り、応募者の適切な期待を育み、企業の信頼性を高めていきましょう!
入社後のフォローの重要性
採用時だけでなく、入社後のフォロー体制もミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。特に入社後1年間は、新入社員が新しい職場に適応するためのサポートを手厚く行うことが求められます。
- 定期的なフォローアップ面談
フォローアップ面談を入社1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、1年後といったタイミングで定期的に実施することをおすすめします。この面談は、社員が感じている疑問や不安をヒアリングし、可能な限り早期に対策を進めるために行います。そのため、社員が率直に意見を伝えやすい環境を作るためにも、業務に直接関わらない社員が面談を担当することをおすすめします。 - 先輩社員との交流機会の提供
入社後に同じ学校出身の先輩社員がいる場合、積極的にその先輩と新入社員をつなぐ取り組みを行うことをおすすめします。共通の話題を持つ社員がいる環境は、新入社員の不安を軽減し、職場にスムーズに馴染むことに繋がります。また、先輩社員がアドバイザーとして定期的に相談に乗る仕組みを整えることで、「悩みを一人で抱え込まない環境作り」に繋がり、離職率の低下にもつながります。 - 認識のすり合わせ
採用時に伝えた仕事内容や職場環境が、実際の業務と一致しているかを定期的に確認することも重要です。採用時の説明と実際の状況にズレがある場合、それを早期に修正することで社員の不満を解消し、定着率を向上させることができます。採用後も継続的にコミュニケーションを取る姿勢が、社員との信頼関係を築く鍵となります!
まとめ
ミスマッチを防ぐためには、採用時の透明性を高めることと、入社後のフォロー体制を強化することが欠かせません。企業が自社の現状や待遇を正確に伝え、応募者と相互理解を深める努力をすることで、ミスマッチのリスクは大幅に軽減されます。また、入社後も新入社員の状況をきめ細かく確認し、適切なフォローを行うことで、定着率の向上と企業の信頼性向上にもつながります。
採用活動をより効果的に進めるために、ぜひこれらのポイントを実践してみてください!


