岩見先生の採用対策室「インターンシップとは?簡単解説!」
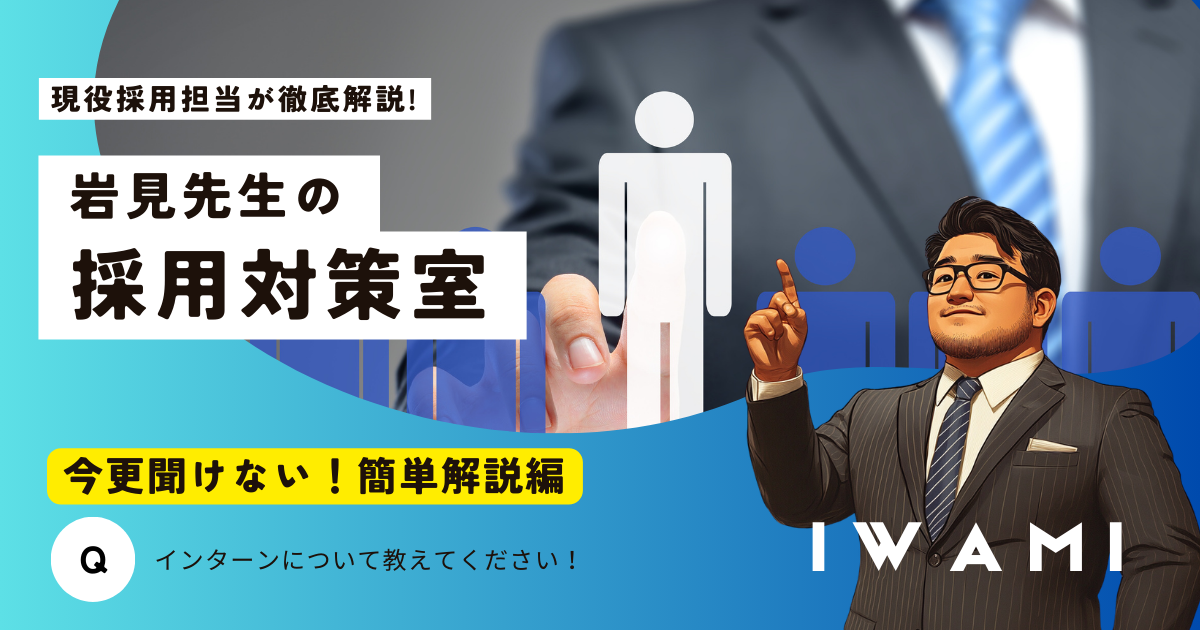
セブンセンスグループの現役採用担当であり、豊富な知識と経験を持つ岩見先生が、企業の採用活動における疑問に徹底的にお答えします。実務担当者だからこそ語れる「成功する採用活動」の秘訣や、実践的なアドバイスを通じて、皆さまの採用活動に役立つ情報を提供します!今回はどのような質問に答えてくれるのでしょうか?教えて岩見先生!

セブンセンス株式会社 総務部 採用課
出身地:東京 趣味:魚釣り・キャンプ
大学を卒業後、小売業界へ就職。5年間販売の業務に携わった後、本社へ配属となり採用担当を約10年間経験。2022年からセブンセンスグループの新卒および中途採用の業務に従事。

「インターンシップを行う企業が増えている印象です。
改めてインターンシップについて、易しく教えてください!」
インターンシップは「学生の就業体験」の場です。
基本を忘れずに検討を進めましょう!


インターンシップとは?基本を押さえましょう!
インターンシップは、学生に実際の「就業体験の場」を提供するプログラムであり、企業や業界を知ってもらうことを目的としています。言わば「学生の将来にプラスとなる就業体験の場」を提供するプログラムです。学生が参加することで得られるのは、単に会社の雰囲気を理解するだけでなく、業界や業種全体の理解を深める機会でもあります。そのため、企業側は学生にとって有意義な体験を提供できる内容でなければなりません。
また近年では、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)の改正に伴い、正式な「インターンシップ」の条件が見直されています。たとえば、就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当させる必要がある)や、実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)などの、条件が定められています。これらに該当しない場合、正式には「インターンシップ」と呼べないため、教育機関との連携の際には注意が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
インターンシップの実情と、企画上の注意点
「学生の将来にプラスとなる就業体験の場」とされているインターンシップですが、企業側は以下のように採用活動の一環として行うケースがほとんどです。
- 学生との接点づくり
企業にとって、インターンシップの最大の目的は、優秀な学生との接点づくりでしょう。就職活動が本格化する前に出来る限り多くの学生と接点をつくり「その後の採用活動を有利に進めたい」という意図の下、企画されるケースがほとんどです。大手企業の中には、インターンシップのエントリーシートを通じて早い段階で学生を振り分けることもあります。「学生の将来にプラスとなる就業体験の場を提供する」という本来の目的とは大きくかけ離れている印象ですが、学生側も企業側のこれらの意図を理解した上で、就職活動の一環として参加するケースが増えているのが実情です。 - 学校側へのアピール
インターンシップのように学生のキャリア形成を支援する取り組みは、学校から高く評価される傾向があるため、企業が自社のイメージ向上を狙い行うケースも多いです。さらに、卒業生が社会に貢献する企業で活躍することは、学校にとってもブランド力向上の一助となるため、企業と学校双方にメリットをもたらしているのです。
このような観点から、インターンシップを行う企業は増えています。しかし、露骨に採用活動へ結びつける姿勢で企画すると「学生の将来にプラスとなる就業体験の場」を提供するという本来の意義から離れた印象を与え、場合によっては企業イメージを損ねてしまう可能性もあるでしょう。
前述の通り「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)の改正もあり、インターンシップの在り方が見直されはじめていますので、「学生の将来にプラスとなる就業体験」を提供する場であることを忘れず、双方にメリットがあるように企画することが重要でしょう。
自社にあった募集方法とは?
さて、魅力的な企画ができたら、募集方法もしっかり検討していきましょう!
インターンシップを成功させるためには、自社の状況に合った募集が重要です。
- 有料媒体の利用
求人情報サイトやインターンシップ専門の有料媒体は、多くの応募を集めたい場合に非常に効果的です。大手サイトのプラットフォームは登録数が多く、短期間で多くの学生の目に留まりやすいのが魅力です。また、媒体には応募者の情報を管理するためのツールが組み込まれていることが多く、応募者のデータを整理しやすいのもメリットです。有料であるため掲載費用はかかりますが、特に初めてインターンシップを実施する企業や、幅広い地域から応募を集めたい場合には、有料媒体の利用を検討する価値があるでしょう! - 最低限のコストで対応
予算が限られている場合は、自社のメディアを最大限に活用しましょう!たとえば、自社のWebサイトやSNSに掲載したり、専用のメールアドレスを用意し、簡単な募集情報を記載した案内を作成するだけでスタートできます。この方法は、コストをほとんどかけずに対応できるため、募集人数が少ない場合や初めてインターンシップを実施する企業に適しています。また、学校との関係を築いている場合には、学校経由で直接案内を配布することで、費用を抑えながらも効果的に学生にリーチできます。
まとめ
インターンシップは学生と企業が深く関わり合える貴重な場です。就業体験を通じて学生が業界や仕事を理解し、企業の魅力を直接感じてもらうことで、ミスマッチのない採用が実現します。
今回、ご紹介したような本来の目的や注意点などを参考に、貴重な人材確保の手段として開催を検討してみてはいかがでしょうか。


