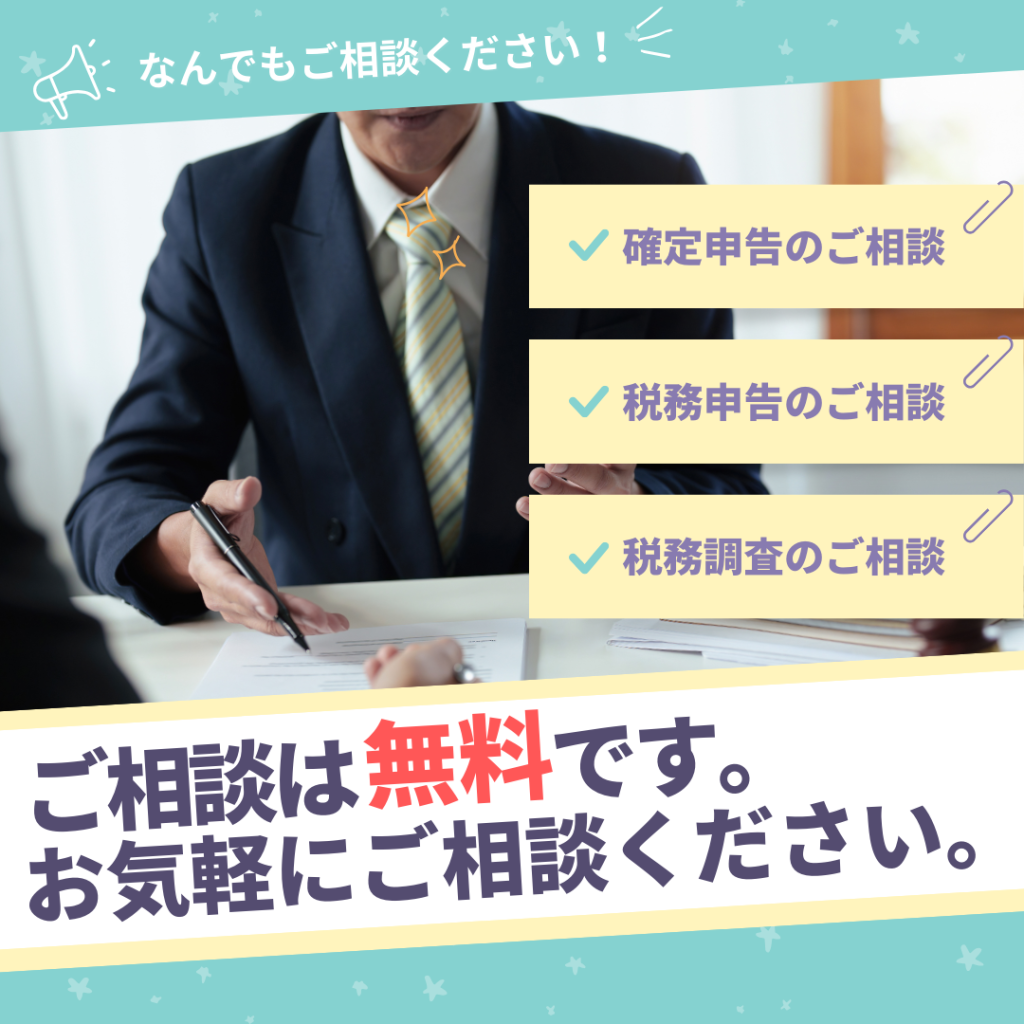居住者判断の常識が通用しなくなりつつある
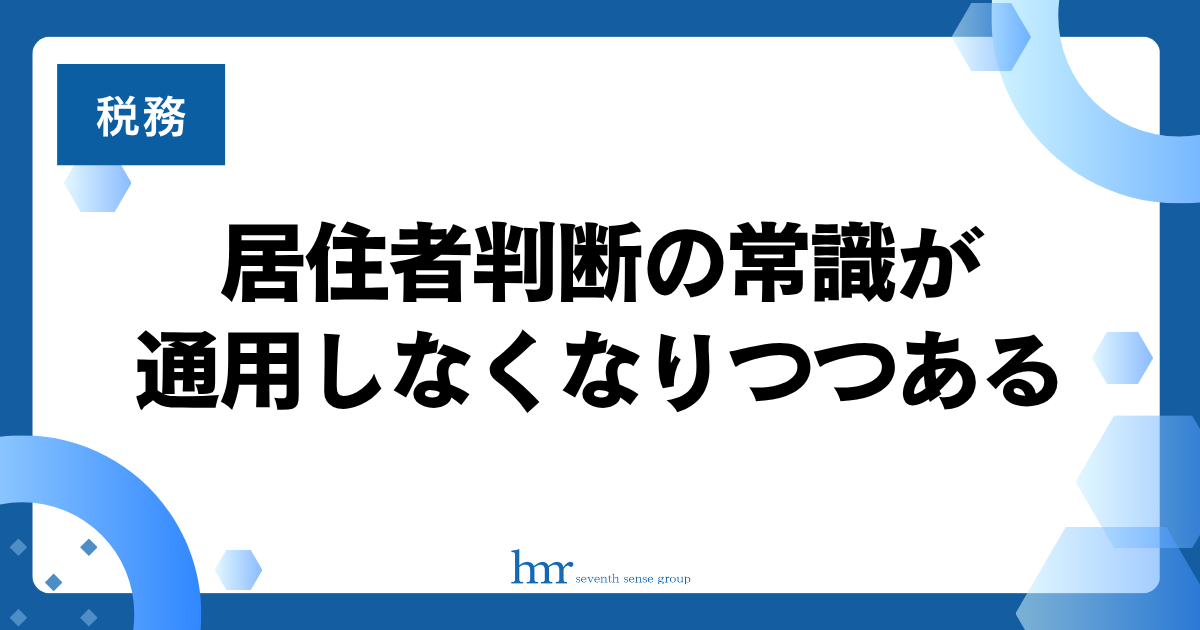
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第五百二十一回目。
テーマは、「居住者判断の常識が通用しなくなりつつある」です。
日本に「生活の本拠」である住所がある居住者は、すべての所得に対して所得税が課税されます。
その反面、住所がない非居住者は、日本に源泉がある所得に対してのみ所得税が課税されます。
このため、住所が日本にあるかどうか、その判定が税務上は大きな問題になります。
とりわけ、複数の国に拠点がある方はその判断で税務当局と揉めることが多々あります。
このような拠点が複数ある納税者の住所の判断基準として、国税庁のホームページを見ると、
①住居
②職業
③資産の所在
④親族の居住状況
これらなどが挙げられています。
具体的には、拠点となる複数の国における、①~④の実態を調査した上で、拠点がある複数の国のうち、客観的に判断して最も関連性が高い国に住所があるという判断を行うことになります。
税務調査においては、非居住者として申告している納税者について、税務当局は居住者と認定して多額の税金を追徴しようとします。
日本の所得税は非常に高いので、富裕層の中には拠点を海外に移し非居住者になろうとされる方が多くいらっしゃいますが、このような方が税務調査のターゲットになります。
ただし、このような富裕層の方の実態について考えますと、当然ですが移住先でも家を持っていますし、家族とともに移住することが多いため、①や④を見てもそれは移住先の国になります。
そうなると、税務当局は日本の居住者とすることができません。
このため、税務調査では②や③の基準を取り上げて、日本に住所があると判断することが多くあります。
海外に移住するとはいっても、海外でビジネスを成功させることは難しいです。
このため、部下にオペレーションを任せつつ、日本にある自分の会社から給与を貰う富裕層の方が多くいらっしゃいます。
加えて、移住前から富裕層の方は多額の報酬をもらっていた訳ですから、日本で不動産投資を行ったり高級車を購入したりするなど、日本に多額の資産がある方がほとんどです。
結果として、職業や資産は日本に関連性があることが多いため、ここを税務当局は攻めて来ます。
とは言え、現在においては、職業も資産も住所の判定としては通用しなくなりつつあることも事実です。
職業が住所の判定に影響を及ぼすのは、職場と住所が遠ければ、通勤が不可能になるからと考えられます。
加えて、資産の所在についても、見知らぬ国で高額投資をするのは、法制度の違いなどカントリーリスクが大きいですから、住所と資産の所在は大きく離れることはない、という考えがあるからと想定されます。
しかし、インターネットが発達した昨今、どこでも仕事ができますし、海外投資などもインターネットで簡単にできる時代です。
このため、職業や資産と、生活の本拠である住所の関連性は密接ではなくなりつつあります。
実際、上記の4つの基準をあげながら、実際の税務調査では日本にいる滞在日数が重視されているようにも思われます。
滞在中は日本で生活していることは間違いない訳で、各国との租税条約などにおいても、この基準が最も重視されています。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs