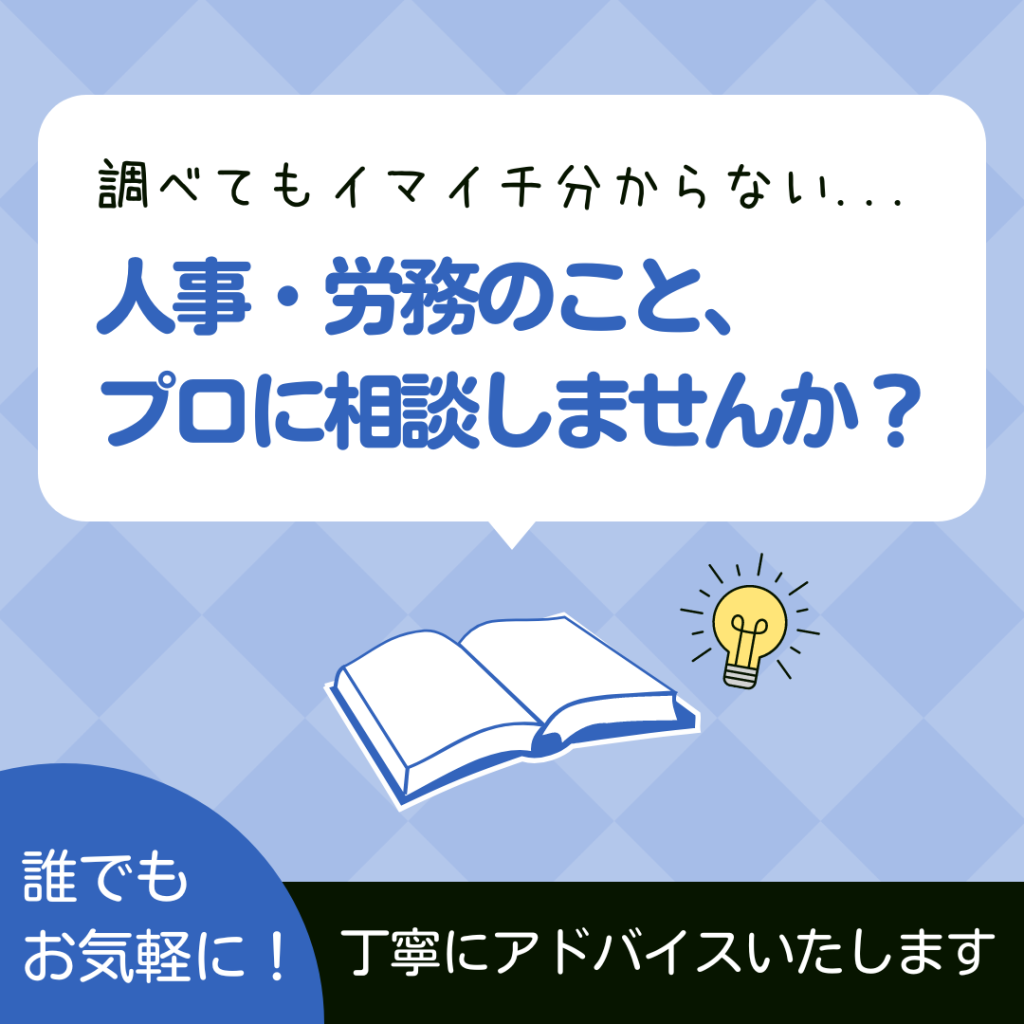育児・介護休業法の改正内容について
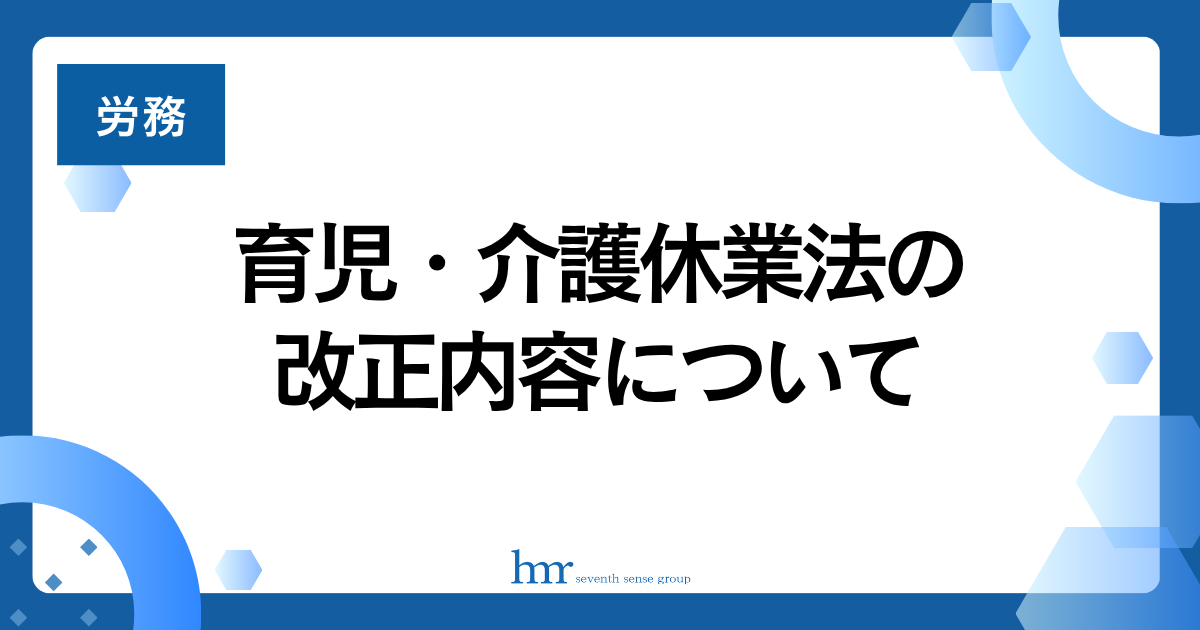
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今回は、2025年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正内容について解説します。
今回の改正は、企業運営に役立つだけでなく、従業員の皆さまにとっても非常に重要な内容です。しっかり理解し、今後の事業運営にお役立てください。
2025年10月1日からは、事業主の皆さまに新たな義務が加わります。
3歳から小学校就学前の子どもを育てている労働者に対して、以下の5つの措置から2つ以上を選択して講じることが義務付けられます。
労働者は、その中から1つを選んで利用することができます。
1.始業時刻等の変更
フレックスタイム制や時差出勤制度など、1日の所定労働時間は変えずに始業・終業時刻を調整する措置です。
2.テレワーク等
1日の所定労働時間は変えずに、月に10日以上利用できるテレワークを導入する措置です。
3.保育施設の設置運営等
保育施設の設置や運営、ベビーシッターの費用負担など、それに準ずる便宜の供与を行う措置です。
4.養育両立支援休暇の付与
1日の所定労働時間を変えずに、年に10日以上利用できる休暇を付与する措置です。原則として時間単位での取得が可能です。
5.短時間勤務制度
1日の所定労働時間を原則6時間とする措置です。
個別の意向聴取・配慮の義務化について
また今回の改正では、育児と仕事の両立を図るため、個別の意向聴取とそれに対する配慮も義務付けられます。
•聴取のタイミング
1.労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出があった時
2.労働者の子どもが3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月~2歳11か月)
•聴取内容
勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量や労働条件の見直しなど、
仕事と育児の両立に関する具体的な意向を個別に聴き取ることが必要です。
•配慮
聴取した労働者の意向に対して、事業主は自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
例えば、勤務時間や勤務地の調整、業務量の見直しなどが挙げられます。
意向聴取は、対面や書面だけでなく、オンライン面談や電子メール等でも行うことができます。
改正の背景とポイント
今回の改正は、少子高齢化が進む日本において、男女ともに育児と仕事の両立を支援し、労働者の離職を防ぐことを目的としています。
男性の育児休業取得率は大幅に上昇したものの、女性との間に依然として大きな差があることから、男性が育児に参加しやすい環境を整えることが重要視されています。
子育て世代の労働者からは、子どもの年齢に応じた多様な働き方が求められています。
企業が柔軟な働き方の選択肢を増やすことで、男女が育児・家事を分担しながらキャリアを継続できる社会を目指しているのです。
今回の改正内容を機に、貴社の就業規則や育児・介護休業規程の見直しをされることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。