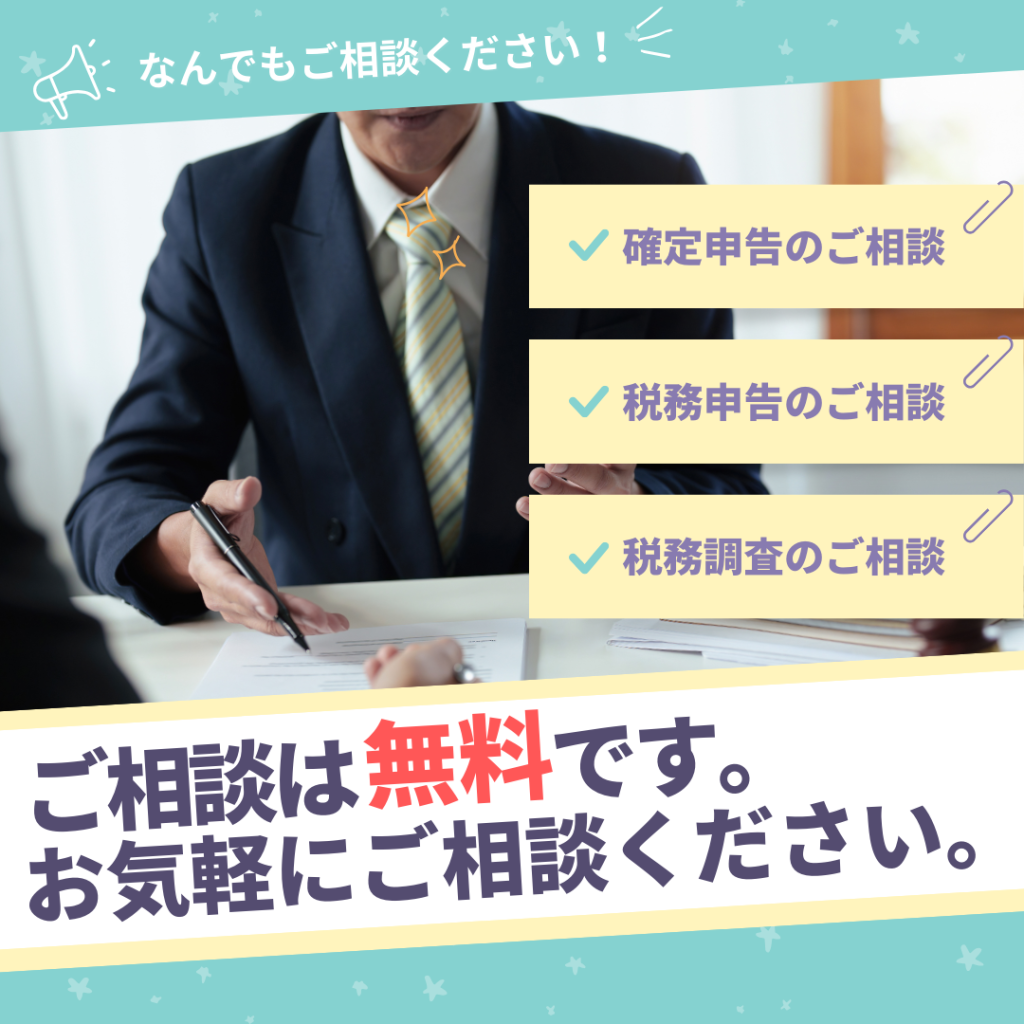定額減税と源泉徴収
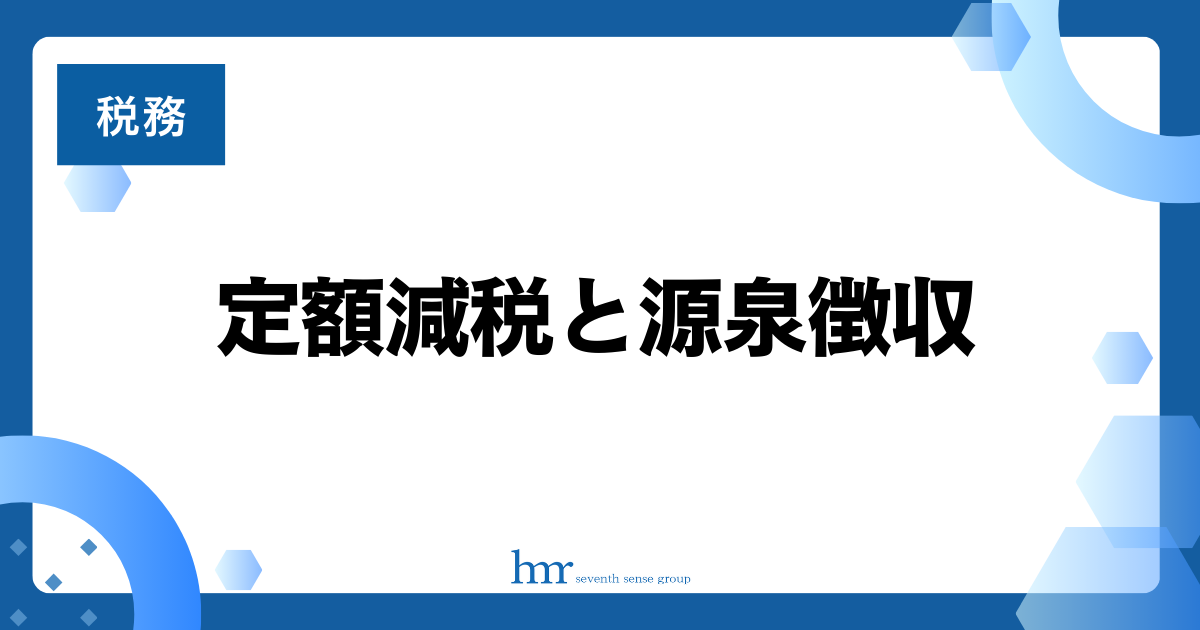
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第五百十四回目。
テーマは、「定額減税と源泉徴収」です。
給与などから所得税が天引きされる源泉徴収においては、三者の関係があります。
すなわち、源泉徴収をする支払者と国の関係、そして支払いを受ける者(受給者)と国の関係、そして支払者と受給者の関係です。
ここで問題になるのは、税においてはそれぞれの権利義務関係、具体的には支払者と国、受給者と国の関係、これらは全くの別物とされている点です。
源泉徴収される所得税は、受給者が負担する所得税を前払いとして天引きしたものですから、所得税の対象である暦年で見れば確定申告で精算されます。
このため、理論的には、支払者が源泉徴収を間違えて少ない金額を徴収しても、確定申告で受給者がその分多く納めれば、受給者が1年間で納めるべきトータルの所得税は変わりません。
しかし、税法ではこの理屈は通用しません。
支払者は法律上正しい税額を源泉徴収しなければなりません。
このため、受給者の確定申告では、その正しく源泉徴収された税額しか精算することができないとされています。
この典型例が年末調整です。
従業員が生命保険料の証明書を会社に提出し忘れたため、年末調整で生命保険料控除を受けられなかった場合、会社は多めに源泉徴収します。
しかし、その多く納めた所得税は受給者が確定申告で生命保険料を申告しても返してもらえないとされています。
建前としては再度年末調整をしてもらい、支払者から返して貰う必要があるのです。
支払者と受給者をトータルで考えれば問題がないのに、それぞれで正しい税額を納める必要があるのが源泉徴収制度です。
こうしなければ、支払う側でいい加減に所得税を徴収するといったことが起こり得るからです。
このため、それぞれの権利義務関係は別物とされており、支払者も受給者も、それぞれ責任を持って税金を納めるべきとされています。
このように支払う側にも重い責任がありますので、実務では元従業員の源泉所得税を取り忘れたような場合には問題が生じます。
これは元従業員から回収すべき税金となりますが、退職後の連絡先が分からないため、回収できないことも多くあります。
にもかかわらず、税務署からは、その元従業員の源泉所得税も会社が自己責任で納めるよう指導されます。
結果として、元従業員から回収できない所得税だけでなく、ペナルティーや遅延利息も課税されます。
支払者に大きな責任が課せられる源泉徴収ですが、それが大きな問題になったのは、昨年令和6年の定額減税でした。
定額減税は、源泉徴収を通じて税金を返すものですから、支払者に責任があります。
減税額は従業員の扶養親族の数などによって異なりますし、当月の支払から引ききれなければ翌月分から控除するなど処理は非常に煩雑でした。
しかし、支払者である会社に責任がある以上、従業員の扶養親族の申告ミスなどもすべて会社の責任となります。
定額減税は物価高に苦しむ国民の救済という目的で行われましたが、このように支払者に大きな負担をかけたものだったのです。
本来、救済であれば、国が直接国民に給付金として給付すべきものと考えられます。
このような場合に備え、給付を的確に行うために、マイナンバーと銀行口座の紐づけも進められてきたのに、定額減税という制度は非常に問題があったと言わざるを得ません。
定額減税についての税務調査は、これから行われることになります。
複雑な制度でしたので、今後処理誤りなど、税務調査で問題になることも多いように考えています。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs