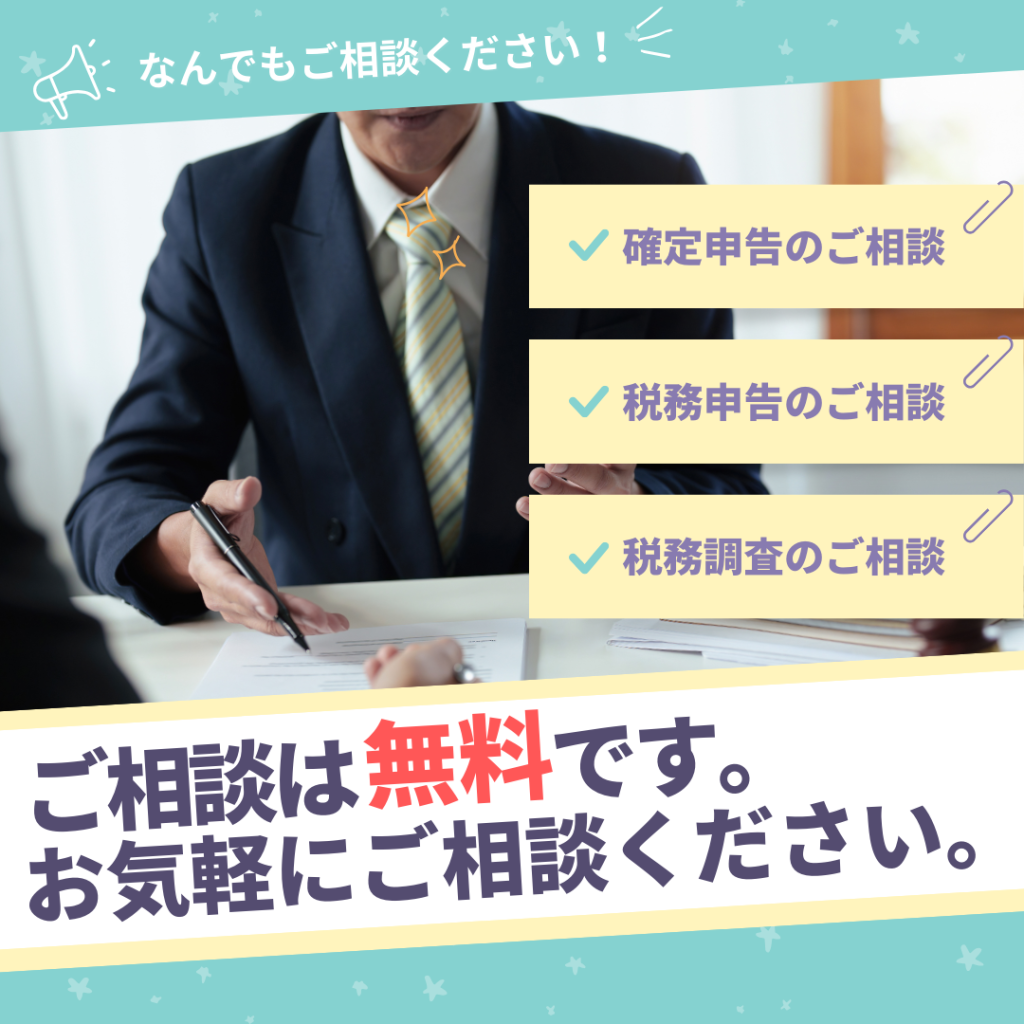「決算書を信用すべき」という違和感
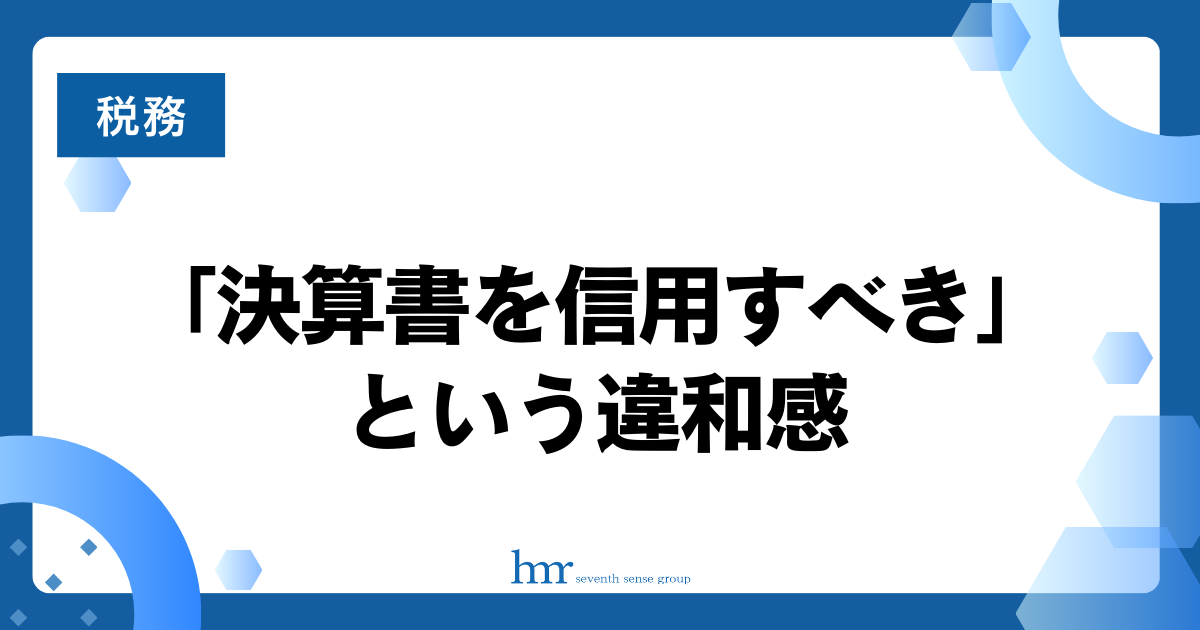
おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第四百九十三回目。
テーマは、「決算書を信用すべき」という違和感です。
相続税で最も問題になる財産は、中小企業でよく見られる、被相続人であるオーナー経営者が会社に貸したお金(代表者貸付金)です。
資金繰りが安定しない中小企業においては、オーナーが身銭を切って会社にお金を入れて窮状を乗り切らざるを得ません。
結果として、多くの中小企業では会社の借金として、代表者からの借入金が計上されています。
オーナーがお金を貸したという建前とはいえ、一心同体の自分の会社に対するものです。
このため、被相続人であるオーナーにとってはこんなもの財産ではないと思います。
実際、回収見込みがない貸付金は評価しなくていい、という取扱いもあります。
このため、経営する会社の業績が悪ければ、回収見込みがないとして、代表者貸付金についてもゼロか額面よりも低額で評価すべきという見解があります。
しかし、判例上、いくら会社の業績が悪くても、代表者貸付金は額面で評価するべきとされ、結果として多額の課税につながります。
困ったことに、近年、この代表者貸付金に対する課税が更に厳しくなっています。
代表者貸付金について、金銭消費貸借契約書などに関係なく、自社の決算書に借金として計上されているだけで課税対象になる、と判断された事例がありました。
この事例では、オーナーと自分の経営する会社は契約など結んでいないため、代表者貸付金は存在しない、といった主張が納税者からなされました。
しかし、会社の決算は会社法に従って厳格に行われるものであるため、決算書に計上されている借金(代表者貸付金)については、実在する可能性が非常に高いとして、税務当局の課税処分が認められています。
この事例が恐ろしいのは、回収見込みがない場合に貸付金を経費とできる貸倒損失の判断と真逆のことが言われているからです。
貸倒損失の要件は非常に厳しく、例えば粉飾決算で生じた売掛金など、決算書に計上していても、実在性が疑われる債権は経費にならないとされます。
このため、貸倒損失を計上する場合には、その債権が決算書に計上されているだけでは足りず、その債権が発生した経緯などを詳細に説明しなければなりません。
同じ債権なのに、貸倒損失を計上する場合は決算書を信用せず、代表者貸付金として相続税の対象にする場合には、決算書を信用すべきとされています。
税金を取ることしか考えない税務当局にとって非常に都合のいい解釈となっています。
なお、元国税調査官の立場から申し上げると、税務調査は決算書の嘘や間違いを見つけるものです。
このため、正しくない決算書の方がむしろ多数ですから、相続税における考え方は到底納得できません。
しかし、繰り返しですが代表者貸付金については、税務署有利にしか解釈されません。
このため、毎期残高をチェックするとともに、早期の完済を目指す必要があります。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs