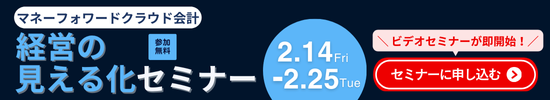東先生の人事労務相談室「仕事と介護の両立に向けた課題と対策」
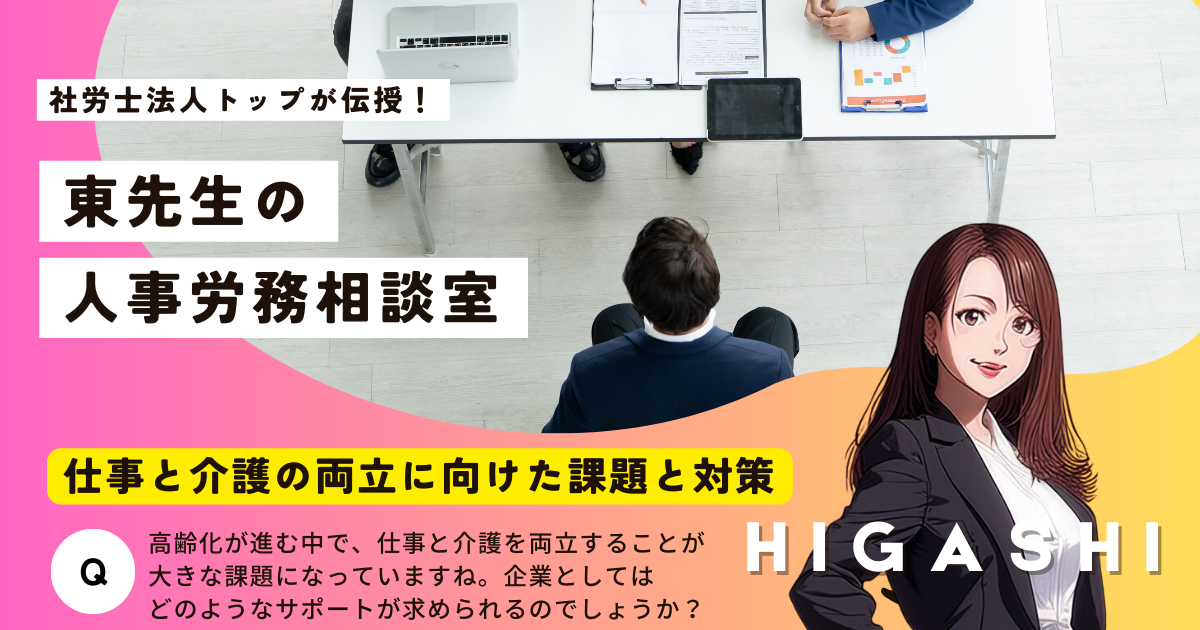
社会保険労務士の東先生が、豊富な知識と経験をもとに、人事労務に関するさまざまな疑問にお答えします。今回は、多くの企業が直面する「仕事と介護の両立」をテーマに、現状の課題や法改正のポイント、企業が取り組むべき対策について解説。従業員が安心して働き続けられる環境づくりのヒントが満載です!仕事と介護の両立支援に必要な知識を、一緒に学んでいきましょう。教えて東先生!

セブンセンス社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 代表社員

「近年、高齢化が進む中で、仕事と介護を両立することが大きな課題になっていますね。
企業としてはどのようなサポートが求められるのでしょうか?」
介護負担が原因で退職するケースも多く、企業として適切な対応が求められます!

介護と仕事の両立が求められる時代
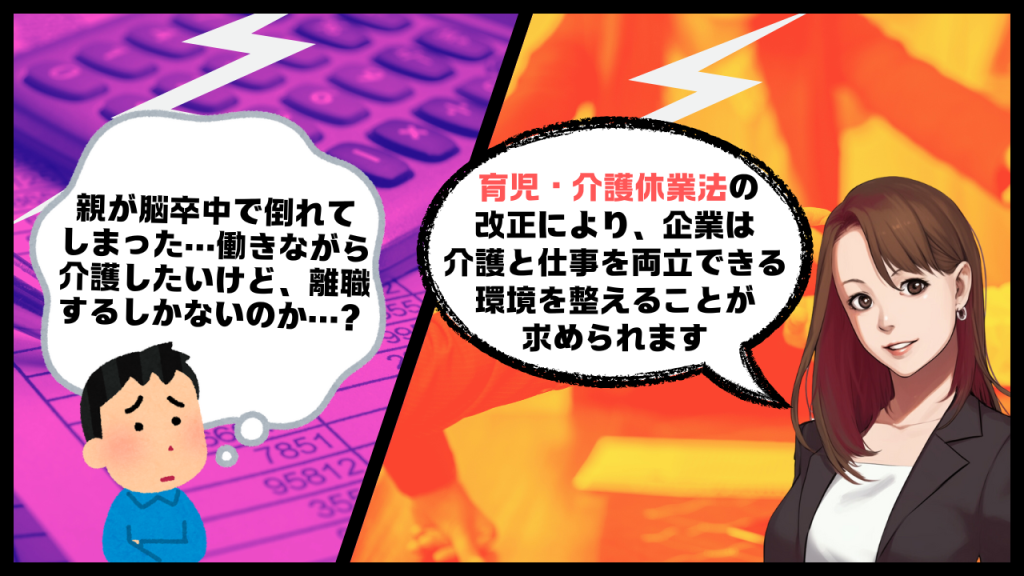
日本の高齢化が進む中、団塊の世代が後期高齢者となることで、仕事をしながら家族の介護を行う従業員が増えており、「ビジネスケアラー(働きながら介護する人)」という概念が注目されています。
現在、介護休業制度では、家族1人につき通算93日間の休業が認められています。介護は突発的に始まり、その後の状況によって必要な対応が変化するため、長期間の一括取得ではなく、必要な時に短期間の休業を取得できる仕組みとなっています。
介護休業は、介護サービスの手配や介護施設の選定に限らず、要介護者の状態の変化や家族の状況に応じて柔軟に活用できます。具体的には、要介護者の体調が悪化した際の一時的な対応や、家族が介護のサポートを必要とする場合の短期間の休業にも利用可能です。
法改正で変わる企業の役割
介護離職を防ぐため、2025年4月から「育児・介護休業法」が改正され、企業にはより積極的な支援体制の整備が求められます。今回の改正では、従業員が仕事と介護を両立しやすい環境を整えるために、 企業が従業員の介護支援制度の利用を促進することが義務付けられました。
「育児・介護休業法」改正により、2025年4月から施行された介護にまつわる内容
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入
(参考: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf )
これまで、介護支援制度が整っていても、従業員がその存在を知らずに活用できないケースが多く見られました。今回の改正により、企業は単に制度を設けるだけでなく、従業員が適切なタイミングで活用できるよう支援する体制を整える必要があります。
さらに、 介護と仕事の両立が可能な職場づくりを進めること も、企業の重要な責務となります。短時間勤務やフレックスタイム制、テレワークの導入など、従業員が柔軟に働ける環境を提供することで、介護負担を軽減し、離職を防ぐことができます。従業員が安心して仕事を続けられるよう、 企業は法改正を踏まえた具体的な対策を講じることが不可欠です。
企業が取り組むべき具体策
仕事と介護の両立を支援するため、企業は 柔軟な働き方の導入や介護支援制度の充実に取り組む必要があります。特に、 介護休業や介護休暇が取得しやすい環境の整備は欠かせません。制度があっても利用しづらい雰囲気があると、従業員は申し出をためらうため、企業は積極的に周知し、利用しやすい環境を整えることが重要です。
さらに、 介護による精神的負担を軽減するサポート も必要です。長期化しやすい介護はストレスの要因となるため、企業はカウンセリングや相談窓口を設置し、メンタルヘルスケアを強化することが求められます。また、介護保険制度や社内の支援制度の情報提供を充実させることで、従業員が適切に制度を活用しやすくなります。
今後は深刻な少子高齢化により、介護する親の人数より子の人数のほうが少ないことも多く、男女問わず、多くの従業員が介護休業等の制度を活用しないと介護離職に至ることになります。
人材確保が難しい近年、これらの取り組みを進めることで、 優秀な人材の介護離職を防ぐことができれば、職場の生産性向上にもつながります。企業は従業員が長く働き続けられる環境を整え、仕事と介護の両立を支援していきましょう。
まとめ
介護休業を取得するケースはまだ多くはありませんが、仕事と介護の両立を支援する環境は、法改正や企業の取り組みによって日々整備されています。企業は制度の見直しや社内研修を通じて、従業員が安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることが求められるでしょう。
▼ 人事に関するトラブルのご相談はバナーから ▼
▼ 録画セミナーなので期間中何度も視聴可能!経営の見える化セミナー 開催! ▼